モバイル閲覧用入り口 - あなたの”本気”はどれくらい?
創作小説 投稿掲示板『登竜門』 『瘡蓋をぺりと剥がすと』
- オリジナル小説 投稿掲示板『登竜門』へようこそ! ... 創作小説投稿/小説掲示板
-
誤動作・不具合に気付いた際には管理板『バグ報告スレッド』へご一報お願い致します。
システム拡張変更予定(感想書き込みできませんが、作品探したり読むのは早いかと)。
全作品から原稿枚数順表示や、 評価(ポイント)合計順、 コメント数順ができます。
利用者の方々に支えられて開設から10年、これまでで5400件以上の作品。作品の為にもシステムメンテ等して参ります。
縦書きビューワがNoto Serif JP対応になりました(Androidスマホ対応)。是非「[縦] 」から読んでください。by 運営者:紅堂幹人(@MikitoKudow) Facebook
- 『瘡蓋をぺりと剥がすと』 作者:模造の冠を被ったお犬さま / リアル・現代 リアル・現代
-
全角6451.5文字大真賀真智は気分転換のために散歩に出かけた。
容量12903 bytes
原稿用紙約19.05枚 -
瘡蓋をぺりと剥がすと
フリガナ オオマガマチ
氏名 大真賀真智
生年月日 昭和58年 9月 6日生 (満23歳)
──どこに行っても嫌われるB型。どういう皮肉か乙女座。この歳になって乙女はない。口にするのも憚られる。
性別 女
──『性別 メス』というのはないのだろうか。あれば迷わず丸を打つのだが。
学歴 葛城大学付属中学校卒業
囹圄高校入学
囹圄高校卒業
職歴 ナンキン部品有限会社入社
主に事務職
ナンキン部品有限会社退社
一身上の都合により
──『一身上の都合により』か……現在、ガソリンスタンドのアルバイト。
賞罰 なし
免許・資格 算盤三級
書道四級
普通自動車免許
危険物取扱者乙種
これで記念すべき三十枚目。腱鞘炎にはならないが精神病を患いそうだ。いや、もう罹っているのか。体重は減っているはずなのに身体が重い。
採光の望めない一室。窓辺に置いたアロエも枯れた。この部屋に引っ越してきたばかりのころは葉肉にも弾力があり瑞々しかった。「傷に効くから」と母がもたせてくれた。
申し訳程度に設置された狭い喫煙コーナのように視界は淡く滲んでいる。白く細い腕が映る。これが肉だとは、血が通っているとは、生きているとは思えなかった。振りかぶって、もっていたボールペンを投げつけてみる。飛んでゆく。埃の溜まったテレビ台の下に転がり込んで、見えなくなった。視界が悪いのは埃っぽいせいではないかと思い至る。
掃除をしようか、そう思う。その前に、自分の掃除をしておこうと思った。掃除の極意はまず道具を補修すること。
お気に入りの服だけをしまいこんだクローゼットを開けて、見繕う。誰かが言っていた。「気分が優れないときは思いっきりおしゃれすべし」。しかし、気分がいいときにはお気に入りの服を着たいと思うものだろう。要するにその訓戒は『気に入らない服は捨てろ』。
フリルとレースで華飾された衣装が目に留まる。寝不足で頭が働かない。フリルの衣装を着るには時間がかかる。頭を切り替えるにはいい準備体操になりそうだ。脱ぐ。貧相な自分の矮躯に苦笑する。この部屋はモヤシの苗床に最適だと理解する。
息詰まる空気をよそに、乾いたアロエは風に嗤い、ぽきりと折れる。
上着をもっていこうと思う。
摩り減らした靴底が月極め駐車場の砂利を撫でる。ざりざりがざり。音が耳やかましい。撫でられるのに嫌がって抗議しているのだろう。私は砂利の抗議を聴きながら優雅に駐車場を横切る。
ホワイトブリムが髪をまとめる役目に就いているが、それを嘲笑うかのように木枯らしが乱れ飛ぶ。風が本当に私の身を切ることができたなら、真に風が自由なのだと認める。木枯らしが吹くたびに足を止め、指先で梳き、匂いを嗅ぐ。
愉快であった。私はまだ意地悪することができ、悪戯されることができる。心のわだかまりを一掃するために散歩を選んでよかった。私は私が踏み躙るものたちから天に捧げられ、私の髪を乱すそれらは私が風の通り道を邪魔していることの証明になる。パニエで膨らませたフレアスカートが上昇気流を捉えたようで、軽い。
目的地に特にあてどはない。『特になし』を記述すれば即刻、不採用を言い渡される書面は部屋に置き去りにした。今はタブーを謳歌する。
寂れたデパート。その最上階。レクリエーションフロアになっている。ゲームセンターを模した一角にあるプリクラ機械の前で、前歯の突き出した男とプリン柄の髪の女がプリントアウトされた写真を覗き込み、はにかんでいる。男が私を見止めた。次第に下卑た笑みに変化し──身を固めた。脇から女に腕を引かれたからだ。鼻の下を指摘される。女に舌打ちし、私を顎でしゃくる。女は私を横目で見、眉を顰めた。心霊写真でも見つけてしまったかのような落ち着かない面持ちでそのまま男を引っ張り込み、蛍光灯がぼんやりとしか点かないほとんど誰も使っていない階段からそそくさと退場する。
上着をもっていない左手をスカートのポケットに突っ込んで、「にんげんはきらい」と呟いた。
恋人たちが降りていった階段の暗がりから人影が現れた。興味本位でまた戻ってきたのかと怪訝に思ってよく見ると、違った。白を通り越して透明ではないかと思ってしまうほどきめ細かい肌をして、フリルの黒いドレスを身にまとい、ホワイトブリムを頭に載せ、純白のソックスを穿いた女の子が上がってくる。女の子はまだこちらに気がついていない。
“自分の二重身を見たものは近いうちに死ぬ”というフォークロアがある。私はあの女の子によく似ている。女の子がもう少し成長してレースの手袋をしたなら、私にすら見分けがつかないほど。
女の子は私と同じ高さまで到達し、そのままくるりと屋上への階段に足をかける。信心にも似た思いを抱いて私は女の子を見守る。「振り返るな」と祈りながら。もし女の子が振り返り、自分によく似た人間を見たらどんな表情をするだろうか。知りたい気もする。だが、いま心にある決断を鈍らせてほしくはない。
そんな小さな願いすら誰にも聞き入れてもらえなかった。視線が交う。
可哀想に。私から湧き出た感情は憐れみだった。私という二重身を見てしまった女の子は死ぬ。見てしまったばっかりに死ぬ。
それに対し、女の子は笑う。悼む二重身を視界に捉えながら、女の子は私にできない微笑を見せる。その微笑は私を受け入れているようにも排斥しているようにも見える。女の子は自分が微笑んでいると自覚していないのだろう。私が一方的に微笑だと思い、救いを感じている。私を受け入れても排斥してもいない。私がそう感じているだけだ。自覚のない微笑みはすべてを受け入れつつ、投げ出している。女の子はすべてに関知していない。二重身に呪殺されるより早く、自分で“キリ”をつける決意だけを宿らせている。
私にはできなかった。屋上への扉が彼女を迎えて、そして閉じた。私と彼女はこんなにも違う。あの強さに魅せられてしまう。あの時、私にはできなかった。今でこそ羨ましさを感じないものの、彼女に激烈な勇ましさを感じる。
思い出したように場にノイズが降ってくる。ゲームの筐体から。掠れた咽喉から。天井に備え付けられたスピーカから。騒々しさが私を苛立たせてゆく。気の抜けた電子音が喧しく。間の抜けた胴間声が姦しく。皮膚に騒音を浴びていなければ生きていられない人間ばかりで吐き気がする。
風はやはり木枯らしだった。街路樹の剪定をする高所作業車が一車線を陣取っているために車線変更しようとしたライフが後ろのセダンに警笛を鳴らされる。ライフはセダンをやり過ごしてから車線を変更した。
サイレンの音は聞こえてこない。
剪定の済んだ禿のケヤキを見上げる。諺の『枯れ木も山の賑わい』を思い浮かべた。街の中で道に沿ってぽつぽつと植えられた木は、山の木より期待されているのだろうが賑わいを感じることはなさそうだ。人気のない映画を観たくなった。
宣伝看板からもっともタイトルセンスの悪いキネマを選んでチケットを買う。邦題『ベンチのお化け』。原題『erotic』。シアタはがらがらで上映開始のブザーが鳴っても中学生の男の子とふたりきりだった。中学生と判明したのは地元の学生服だから。数ある席の中で私と中学生はひとつ席を挟んだ同じ列に座る。その席がスクリーンの正面にあたるからで、示し合わせて座ったのではない。暗く閉じてゆく。
デートの帰り際に公園に立ち寄ってベンチに腰掛けようとしたところで彼氏に身体中を撫で回されて恋心が冷めるのを感じた彼女は次のデートでも彼氏が公園に寄る素振りを見せたところで完全に愛想が尽きて別れを言い渡したが逆上した彼氏に髪を捕まれ公園の茂みに引き摺られレイプの恐怖を感じたため悲鳴を上げようと思ってもうまく咽喉が機能せず彼氏が振り上げた拳に対してもただただ顔を背けるだけだったのだがしばらくしても打撃が降りかかってこないことに疑問を感じて恐るおそる顔を上げると前回のデートのときにも向かいのベンチに座っていた青年が今は彼氏の腕を捻り上げていて青年が彼氏の顔の前にスッと手をかざすと意識を失ったらしい彼氏がゴム人形のように倒れた。
青年はそのまま前回にも座っていたベンチに腰掛け直す。顔は彼女に向いていたが、しかし無関心であるような態度を続けている。ある夜、公園の脇を通りかかった彼女は相変わらず青年がベンチに腰掛けてところを目撃する。正面のベンチに座ってみるが、またしても反応しない。見ているのか見ていないのかよくわからないが嫌がっている様子はなくただベンチに腰掛けているだけの青年を見て、彼女はそれが青年の日課なのだと合点する。あくる日もあくる日も見ているのかもわからない青年の前に座って見つめあう。
変哲のない公園の二脚のベンチにそれぞれ向かい合って腰掛ける男女。話すことはなく、男のほうは女を視認できているのかも不明なふたりのシーンが延々と続いた。
邦題から気取るならば、男はお化けなのだろうか。私が映画を観たいと思った欲求は満たされていた。私が立ち上がると、ふたつ隣の中学生も遅れまじと立ち上がる。私はシアタを後にした。
彼女はもう落ちただろうか。
きっと私が映画を観ているときに実行された。あの微笑に干渉できるものが屋上にあるとは思えない。
目が明かりに慣れる。サイレンの音は聞こえない。
木枯らしがびゅうびゅうと通り過ぎる。土手の上を歩いていると実際の風力より禍々しく聞こえる。空威張りと同じ。相手を脅しつけて自分を大きく見せるのは、肝が小さくて臆病だからに過ぎない。私の身を切るには到底及ばない。痛みをすら感じない。
人にかかずらわないように生きているといちばん厄介なことは、お腹が減ることだった。食べないでいようと思っても二日が限界で、食欲を満たすことを優先してしまう。外出する。写真を撮るだけにしておこうと思ったが、早い夕食を済ませておくことにしよう。自動車学校の隣に建っている喫茶店は証明写真も撮ってくれる。
ドアを開くと鈴が鳴り、カウンタの奥にいた中年男性が私を一瞥する。客は誰もいなかった。
「履歴書の写真を撮りたいのですが」
カウンタから出てきた男性は手振りで誘導する。喫茶店とは別に設えた撮影室は狭苦しかった。
「その格好で撮るの?」
珍しいことに、そこに揶揄する響きはなかった。
うっかりしていた。上着ももってきていたが、それも証明写真に相応しいとは言い難い。人と話をするのが苦手で、うまく伝えられるか考えると余計に舌の動きが鈍くなる。身振り手振りがやけに大げさになる。
垂れた眉毛の下にある窪んだ目が私のなにかを捕らえた。おそらくは、左手。
「背格好は似ているから、……ちょっと待ってて」
奥に消えて、階段を上がる音が聞こえた。
撮影室の小さな椅子に座っていると手持ち無沙汰になってしまった。喫茶ルームのテーブルに立てたメニュを開くと、素っ気ない明朝体で『コーヒー』と書かれていた。
「よければこれを着てみて」
テーラードジャケットとタートルネックのセータは見ただけで上質と知れるものだった。
「でも」
「気に入らないかな」
「いえ、でも」
「ああ、私がいては着替えられないか」
撮影室に誘導したときと同じように、目で呼ぶ。二階の部屋に案内された。プライベートな空間だ。着替えたら降りてきて、と言い残して階下に降りていった。
女性の部屋だ。私の部屋より少し狭い。ひとり暮らしのアパート住まいと一軒家の部屋と比べても意味のないことなのかもしれない。女性らしいグッズが各所に配置されていて温かみが感じられるのだが、人間がここで寝起きしているようには思えなかった。本棚がきれいに掃除されているのだが、どの本も閲覧した形跡がない。
「似合っているね」
カメラから顔を上げた男性は私を見るなりそう言った。
上下がちぐはぐなので一般には似合っているとは言えないだろう。しかし、証明写真なら十分だ。計四枚撮り、そのうち二枚を男性に渡した。
「面影を重ねて見ているのではありませんか」
ぴくと身体を震わした。目が合う。
「カレーライスをください」
この服の持ち主と二階の部屋の持ち主は合致するだろう。そしてそれは、男性の娘ではないだろうか。推理と呼ぶほど根拠のないものではない。
これで、薄くも人との繋がりができてしまった。店主と客という間柄よりはよほど濃い。これからは進んで繋がりを作っていかないと立ち行かなくなる。これも人付き合いの練習と思って耐えるしかない。
「お待たせしました」
「自傷癖のある方でしたか」
この問いには「YES」と答えるだろう。
カレー皿が大きく音を立ててテーブルに着く。ルーは黒め。ご飯が多め。スプーンはピカピカ。
「はい。娘は、私の前ではいつも明るく振舞っていましたが……」
自傷癖もちは当たっている。娘だというのも正解。まさか飛び降りではあるまいな。違うとはわかっていてもデパートで出会った彼女の顔が浮かぶ。死に神すら見まごうだろう似た顔。
「生きていれば今年で26歳になります」
「どうやって亡くなったのですか」
口にしてから失敗したと思った。私が訊くべきは生前の姿だ。
「死亡が確定するのは来年。行方不明者は五年経つと死亡と看做されるそうです」
その口の動きは実感が伴っていない。おそらく、来年を過ぎても娘の死を受け入れることはできないに違いない。
「どちらにせよ、その服を着て気持ちのいいものではありませんね。すみませんでした」
気遣いをされていることに気付いたのは一拍置いて後だった。娘の代わりとして代弁し、聞き手として辛い過去を吐き出させてやろうとしていた。成り上がっていたかもしれない。ドラマに当て嵌めていた。現実は私の想像よりよほど複雑な動きを見せる。
「カレーがおいしいです」
「それは良かった」
カラランと鳴る扉の向こうで男性が手を振る。
二十九社に相手にされなかった理由を今ようやく突き止めたような気がする。
合理に則っても裏切られる。
生身の人間はノイズが多い。
状況状況で波に乗るが肝要。
溜め息が出る。それらは孤独を紛らわすために強固に張り巡らした武装だ。今まで卑屈になって一生懸命塗り固めてきた武装を削岩機で一気に崩すことはできない。過去の自分を全否定するぐらいなら人間失格で構わない。
土手からぬっと現れた夕日はひしゃげている。
部屋の扉を開けるとむっとした空気が流れ出る。自分の部屋にも拘らず、よくこんなところで生活できるなと思ってしまう。我慢しているわけではないが、慣れてしまうのだろう。
締め切られたカーテンを開ける。部屋の空気が攪拌されて埃が舞い遊ぶ。ベランダからも夕日が見えた。机の上に置かれた履歴書に西日が差す。
スティック糊はどの引き出しに入っていただろう。そうだ、貼り付ける前に裏に名前を書かなければいけないのだった。選考前に写真が履歴書から剥がれたら誰の写真がわからなくなる。ボールペンは。テレビ台の下に投げ込んでしまっていた。覗き込むと、埃がうずたかく堆積している。脱ぐ。フリルのついた衣装はここではモップにしかならない。不恰好な下着姿でテレビ台の下を探る。かつん、と指先に当たって奥に入り込んでしまった。まどろっこしい。配線を外してキャスタのストッパを起こす。テレビ台を退けると見事に埃が四角を形作っている。ボールペンは。あった。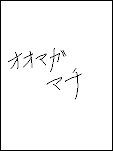
-
2007/08/19(Sun)12:41:20 公開 / 模造の冠を被ったお犬さま
http://clown-crown.seesaa.net/
■この作品の著作権は模造の冠を被ったお犬さまさんにあります。無断転載は禁止です。 -
■作者からのメッセージ
書き物をすればするほど、どんどん難解なものになっている。本人が言うのだから間違いない。わざと難解にして煙に巻き、物書きの権威を無闇に高めようとしているのではないから、その効果はマイナスにしか表れない。読み手に不親切な文章だ。
心情描写を増やし、読み手と同期させれば良いことはわかっている。しかし、それを良しとしない私の理念というものがある。“おしゃべりは信用ならない”というものだ。人間はそんなにきっかりと思考して行動しているのではない。小説の人物のように自分の行動にいちいち言い訳をする人間がいたら気持ち悪い。過去の蓄積を踏まえた上で選択を行うことができる。過去は省略できるのだ。さながら、アドベンチャゲームの『既読はノーウェイト』で読み飛ばすように。この書き物の主人公は23歳という設定をしている。この人物に完全に同期したいと考えるのなら生まれた瞬間から心情を読んでゆくことなのだが、残念なことに私はそれを書いていないし書こうと思わない。
回避の一般的な手法としては登場人物を単純化することが挙げられる。定型化することも有効だろう。それは私も認めるところだ。だが、あげつらったそれらの手法に委ねないのは単純に気に入らないからである。そんな薄っぺらな人格では書いていても満足できない。
そのわりに「お前は人間が書けていない」と言われることがある。この指摘にはふたつの要因がある。
ひとつには、私が私以外の人格を書けないことだ。人間は誰しも複数の顔をもっているのだが、その顔ごとに人格を与えるのか、すべての顔をひっくるめてひとりと看做すのかではまるで違う。顔はその字のごとく『面』であり、ひとつの顔は『一面』でしかない。多角的でない。薄っぺらな人格では満足できない私は、登場人物にかならず二面以上を与える。これは、自分の仮面を剥がして与えているイメージだ。私も相当に仮面をコレクションしている身ではあるが、やはり数には限りがあり、つまりは人格にも限界が生じるのだ。私はもっと他人に触れ、その人格を許容する必要がある。それが仮面の獲得となるのだ。
もうひとつの要因は、私の生み出した登場人物たちが私自身であるということを考慮すれば悲しいことに、人格を理解されていないことにある。仕方のないことかもしれない。私の書き方に読み手への優しさが不足しているのだから、読み手に理解させようと強制するのは酷なことである。ではどうだろう、読み方を変えてみるというのは。自分を主人公に同期させず、あくまで他人として観察するように読んでみたら案外と面白いかもしれない。彼らを他人と看做すのは私には到底できないことであるが。
って、お前おしゃべりだな。
- この作品に対する感想 - 昇順
- 感想記事の投稿は現在ありません。
- この作品の投稿者 及び 運営スタッフ用編集口
