-
『魂無いきみが残り香で誘う【ノーマルエンド】』 ... ジャンル:未分類 未分類
作者:模造の冠を被ったお犬さま -
あらすじ・作品紹介
先輩に告白するも恋破れた僕。相変わらずの毎日を送る僕たちに突如アクシデントが襲いかかる。標的にされた先輩は、しかし被害者になることができなかった。気配りと心遣いと思いやりがカラカラ空回りする、壊れやすい時代のための新青春エンタ。
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
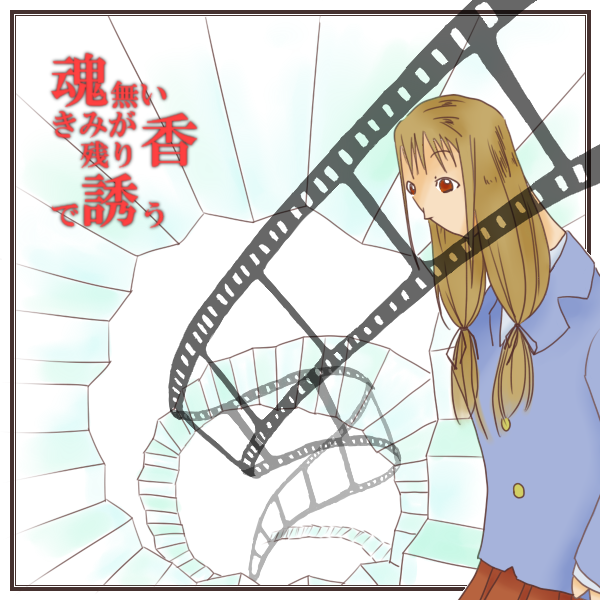
魂無いきみが残り香で誘う
『電話してもいい?』とeメールを打ち『いいよ』と返ってきたので、「先輩に話したいことがあります」と伝えた。
鏡の前で全身を隈なくチェックすると、少し顔の上気した少年が映っている。目ヤニなし。鼻毛なし。ニキビは、仕方なし。髭なし。髪のハネなし。問題なし。解答もない。玄関を飛び出した。
先輩は「タモリみたいだね」と言った。「知らない? タモリってさ、テレフォンショッキングなんてやってるけど、ホントは電話が嫌いらしいよ。『電話するときは電話すると電話しろ』なんて名言が残ってるぐらい。それじゃ、電話なんてできないじゃんね」
僕の家と先輩の家の中間にある喫茶店ではオープンカフェを意識しているのか、角の二面がガラス張りになっている。珈琲の味は可もなく不可もなく、そこそこ愉しめる──と思うのは、経験則であって実感ではない。今の僕は珈琲の味を楽しめるほど余裕があるわけではないのだ。
先輩の言いようでは、タモリのエピソードは相当古いらしい。当時はケータイにeメール機能が付いていなかっただろう。いや、ケータイそのものがないのかもしれない。だから、不可能ごとの笑い話になる。僕はようやく、自分がタモリにアポイントメントをとろうと試みる知り合いなのだと気付いた。先輩は自分をタモリに見立てていたのだ。
動態視力に訴えかけるジェスチャ、手を振る。キャンペーン中であるかのように過剰なそれを目の端に捉えた。先輩だった。
僕が気付くとガラス越しににっこり笑う。そして腕時計を探り、生真面目な顔になったかと思うと、野球のアンパイアのように腕をセーフに形作った。先輩はいつもなにかのジャスチャがキャンペーン中だ。
「ギリギリセーフ」店に入るなり台詞でも表現する。
「僕もいま来たところです」
先輩は親指と人差し指の角度を九〇度にして名探偵のように顎に当てる。ニヒリストになりきれない笑顔で、
「ふふふ、待ち合わせの定型文をどうもありがとう。しかし、氷しか残っていないグラスはきみの言葉を裏切っているな」
先輩の家との中間地点を選んだつもりだったが、家にいたのではないらしい。いつも以上にテンポの速い口調からして、かなり急いで来てくれている。口調が速いということは呼吸も速い。
「しかも、お替わりしている」
なぜわかるのだろう。伝票は裏になったまま、テーブルの上にグラスはひとつ、ストローも同じ。まさか、僕の尿意を読んでいるとでも。そんな芸当ができてもおかしくないのが先輩だった。
「ただの後輩のために遠くからはるばるようこそおいでくださりました。お世辞程度の嘘など、いくらでも吐いてみせますよ」
「ただの後輩じゃないよ」僕はなにかに期待する。「おねーさん、可愛い後輩のためならなんでもしちゃう」
可愛い。意味の幅が広すぎて茫洋としたイメージしか伝わらない。後輩の枕詞としての可愛いだろうか、おねーさんに対比する弟としての可愛さだろうか、それとも先輩は僕という主体を可愛いと感じてくれているのだろうか。
先輩は直観力も思考力もあるのに、それを的確に伝達する能力が低い。だから先輩のもつイメージまで、いまひとつ茫洋としていて曖昧なままだったのだ。
「二段階に断りを入れてまで話したいことってなに? おねーさん相談に乗っちゃうよ」
真剣に話を聞く態度と気楽に話をさせる態度を同居させる。そんな真似ができる人間は同世代にひとりしか知らない。大人にだってそういない。
「虐め、とか?」
絶妙な態度のブレンドを帯びた瞳で覗いてくる。真剣味六〇%、心配性三〇%、庇護欲一〇%、気安さ〇%。増量中につき、心配性は二割アップし心配性が全国心配機構規定の基準値を超えるため、老婆心へと名称を改めます。
「違いますよ」先輩はいつもオーバなんだ。
事実として、虐められている。でも、僕は先輩の身振りと違って大袈裟にするつもりはない。被害者の目にだけ映ることができ、加害者の目には映らない、映るとしたら可愛がり。性根の曲がったものには王様の衣が見えないように、虐めっ子には自分の行為が見えていない。
体育会系の、それも格技をしようというのだ、これぐらいの虐めで音を上げていては続けられない。そんなことで先輩を呼び出したりしない。
「先輩は好きな人います?」
大きく丸い目がさらに大きく開かれる。
「おおう、恋愛相談か。なになに誰に恋焦がれちゃったんだい?」
実は、かなり勇気を振り絞って訊いてみたんだが。ステータスとして恋人がいるかどうかを訊くのと、告白前の確認で好きな人がいるかどうかを訊くのとでは雲泥の差がある。
「ん? なにその反応。まさかそのお相手が不肖わてくしではあるまい。なーんて。自意識過剰な人間って見てると腹立つよね。──そのこくんって頷きはなんだ。腹立つか、そんなに腹立つのか」
本気で傷ついた顔をするので僕まで先輩のお株、オーバリアクションで首を横に振ってしまった。
「いいよ、無理に慰めなくても」慰めじゃない。「じゃあ、なんで頷いたのよ」先輩はまたも名探偵のポーズ。「ははあん、なるほど。そういうことか」にやりと笑う。「頷いたのは『腹立つ』じゃなくて『お相手が不肖わてくし』なのだな」間・間・間。三秒ほどの間。「はっ、それってどういうこと? こういうこと? そういうことで合ってるの? えっ、ホントに?」先輩は混乱中。英訳するとコンフュージョン。なんで翻訳しているのか、僕はどうやら暴走中。
でも、ここできっちりけじめをつけておかないと。
「僕は先輩が好きです。付き合いたいです。付き合ってほしいと思ってます」
先輩の反応は──よくわからなかった。いろんなことに思いと考えを巡らし、思いと考えをばったばったと薙ぎ倒し、それでもまだ押し寄せる無限の思考を相手に検討と健闘を重ねている。僕を相手にしていない。傍目には、呆然としているだけ。
「愛の告白だよ、ね。
嬉しくて、それに初めてだから信じられなくて。きみの気持ちを疑ってるわけじゃないよ。まさかお相手がわたしとはね。うん、とても嬉しい。好きという気持ちがここまで純粋に人を幸せにするとは、ちょっと思いもよらなかった。
返事はすぐにしたほうが良いのでしょうか」
「ステータス異常を回復してからでいいですよ。エスナかケアラルを唱えましょうか? フライパンを使って混乱から回復するゲームもありましたね」
まず、自分に使え。
「ちょっと待ってて。もう少し喋ったら落ち着くと思うから。変なことを言ってもあんまり気にしないでね。待っててくれたら、ちゃんと返事するから。
初めて会ったのはいつだっけ。部活の顔見世だったかな。初めて、というのなら体験入学のときになるのかな。ごめんね、いつのまにかお喋りする仲になってて、ファーストコンタクトって意識してなかったな」
「先輩からしたらそれが順当ですよ。去年の入学式の日のこと、憶えてます? 校門で新入生の胸にコサージュを飾る係に就いていましたよね。実は僕、あの日が初めてネクタイを締めた日なんです。うまく結べてなくて、曲がってたみたいで」
先輩はポン、と手を打つ。「いたいた。結び方から間違ってる新入生が、いた」
「え、曲がってるだけじゃなくてそんな初歩から間違ってたんですか。だから最初から締め直したのか。ネクタイをしゅるっと外すと、手馴れた様子で結んでくれました。最後にきゅっと締めて、『行ってらっしゃい』。まともに顔が見れませんでした。後ろに次の新入生が並んでいたし、気恥ずかしくてそそくさと逃げるように立ち去りましたっけ。すぐに、なんで顔をはっきり見ておかなかったんだ、と後悔したんですけどね。
憶えていたのは、僕の胸先に鼻を突きつけるように近すぎる、先輩の頭から立ち上る微かなシャンプーの香り。これは、一目惚れって言うんでしょうか。匂いだから、一嗅ぎ惚れでしょうか」
先輩は「なにそれ」と笑った。
淡々と話しているように見せているが、内心は非常に恥ずかしい。先輩にとって何気ないことが僕にとってどれだけ特別なことなのか、恋焦がれちゃう結果となったのか本人を前にして述べる。クールを信条とする僕にはハードルが高かったようだ。
それでも、先輩が笑ってくれるならいいやと思える。僕がどれだけ先輩のことを好きか伝えておいて悪いことはない。そうしてフられてしまうと傷心がより深く抉られることになるが、伝えきれずにフられるよりは何倍もマシだ。恋心を怨霊にしたくない。
「それ以後、匂いを意識するようになりました。学校で女子のフレグランスを嗅ぐと、『違う』と条件反射で判別するようになってました。笑わないでくださいよ。女子の後を付きまとって鼻をひくつかせていたわけじゃないんですから。たまたま嗅いだ匂いが無意識下で勝手に照合されて……それもちょっと変ですね。
そうしてずっと『違う』と感じ続けていると本物が恋しくなってくるんです。このときはまだ、先輩が使っているシャンプーを見つけ出せれば満足できたかも知れません。でも、メーカもなにもわからずに匂いだけでシャンプーを買うのって難しいでしょう? 匂いはうまく言葉にできないし、男の僕がシャンプーに拘っているなんて思われたくなかったんです。今にして思えば、シャンプーを探すなんてことは考えもしなかった。匂いではなく、先輩が好きだったのでしょうね。恥ずかしいだけが原因じゃなくて、シャンプーを買うなんて選択肢はなかった。ああもう、あのときすでに匂いだけじゃ満足できなくなってたのか」
「好き」の言葉に改めて頬を赤らませる先輩を見て、僕まで照れくさくなる。
「授業の合間の休憩も、先輩の影を探して校舎中を彷徨い歩いていましたよ。もう、笑うなら笑ってください。どうぞお好きに。自分じゃ笑えませんから。
で、見つけたんです。放課後なにげに窓の外を眺めていると、第三棟校舎の一階を先輩が歩いているではありませんか。直線距離にして20m程。ここまで匂いが漂ってくるはずもなく、窓枠に囲まれた胸部までで、ほんの一瞬だけ横顔が見えただけなのに、僕は同一人物だと確信しました。窓越しに目で追います。断続的に見える姿、回転の遅すぎる走馬灯のよう。これほどまで窓を熱望したことはありません。喩えマイホームをもつときだって、ここまで窓に執着することはないでしょう。廊下にある最後の窓も通り過ぎて、突き当たりに差しかかっていました。僕は気が気ではありません、よく考えもせずに先輩の消失点へと駆けつけていました。先輩と初めて会った日にもらったパンフレットを頭に展開して、どこに向かったのか考えます。自分の失敗に気付いたのは、目標地に着いたのと同時でした。廊下の突き当りといっても、階段がある。階段から二階・三階へ向かったのなら、そこからさらにどこへ向かったのかなんて範囲が広すぎて追えない。冷静を保てていれば、教室に留まって踊り場の窓に先輩が映るか確かめていたでしょう。でも、もう遅い。現場に到着している。最後の窓がある先輩消失点から廊下の突き当たりまで、先輩が向かったと思われるのは五ヶ所。まずは左手にある階段。ここを通ったとしたら、その先からどこへ行ったのかなんて考えるだけでも大変。次に突き当たり、非常口がある。この先は校舎の外。右手奥、理科室。人の気配がある。その手前、理科準備室。鍵がかかっていて入れない。右手手前、空き教室。
なんて、もって回った言い方をしても先輩にとっては自分のことだからどこに行ったのかなんてわかりきったことですよね」
雰囲気に呑まれているのか、わくわくしながら話を聞いているので、つい確認してしまった。先輩の頭上に豆電球が点った。
「でも、入学したての僕にとってそこにある教室の教室名を言い当てるだけで精一杯ですからね。その教室がどの時間にどんな人がどんな名目で使っているのかなんてわかりません。
本命、理科室。希望的観測含む。
対抗、階段。信じたくない。
単穴、非常口。鬼が出るか蛇が出るか。
連穴、理科準備室。本命とのコンビネーション。
大穴、空き教室。先輩の弱みを握るルート。
番外、階段下の用務具倉庫。考慮外。
まず手始めに、理科室の扉を開きました。集まる視線。流れる冷や汗。今ならそれが科学部の実験中だったとわかりますが、当時は『なんで一年坊主がこんなとこに入ってくるんだ』という排他の目で睨まれたことしかわかっていませんでした。開けたときと同じ唐突さで、僕は理科室の扉を閉じます。ばつが悪くなると逃げ出すのは、先輩に会ったときと変わりませんね。でも、同じ轍は踏みません。扉を閉める前に、全員の顔を見渡して先輩がいないことを確認していました。なんという早業、今の僕が当時の僕を学校生活の知識で負かしていたとしても、ハングリな集中力では敵いません。同じことをやれと言われても無理です。強盗が立てこもった銀行に突入するSITにだってきっと無理です。そこにいる全員がこちらを向いていなければできない荒業でもありますからね。
かくして、本命が消えました。候補を五つ──番外を含めると六つ挙げたのですが、僕の中ではほとんど二択でした。つまり、理科室の可能性がなくなれば残っているのは階段。階段、それはもう絶望のコングロマリット。第三棟校舎はいわば特別教室棟。理科室をはじめさまざまな教科の教室があり、また今の時間であればそこは部室へと変貌する。
理科室は科学部が、
社会科室は新聞部が、
音楽室は合唱部が、
図画工作室は美術部が、
家庭科室は調理部が、
技術室は無線部が、
習字教室は茶道部が、
物置からビフォアフタ暗室は写真部が、
己が要塞と陣を構えている。
おおよそ文化部と呼ばれる部活が集まり犇めき合う激戦区、それが第三棟校舎。先輩の所属部を知る由もない僕がそれを調べようとするなら、科学部に突入したときのようにたったひとりのパルチザンになるしかない。しかし、そんなことは二度とできない。戦争は人を人でないものに変えてしまう。僕の精神は耐えられなかった」
目を合わせる。告白したときと同じ、口を開けたまま恍惚としている。しかしこれはもう単純に、なにも考えていない状態。興に乗じてふざけ過ぎたか。
お話が急に途切れて、興味津々な瞳が所在なげに彷徨う。
「せ、戦争ってダメだよね」
視線が合うこと、会話中に間が空くことに苦手意識があるようだ。お間抜けな穂の継ぎ方。うん、戦争は良くないことだよね。
「特攻しないからって先輩を探すことを諦めたわけではありません。そこはおいおい話すとして──ペースを上げて話しましょうか。ピッチを上げて話すことは僕にできませんから。クイズの答えを話すのが目的ではないにしろ、プロセスを丹精しすぎました。弁解させてもらうなら、僕も浮かれ気味ってことです。このままでは、いつまで経っても先輩の返事がもらえませんからね。
階段のことは保留で、頭を切り替えて穴を埋めます。単穴、連穴、大穴。単穴の非常口を覗いてみると、木立になっています。学校の裏手に当たる場所で、湿った土が顔を見せている。運動場に出るにも校門に出るにも遠く、非常口といったって、校舎と木々の間をすり抜けるような狭い通路では地震時の避難経路としては不合格は確実で、また火の手が上がるとしたら隣にある理科室か上にある家庭科室ぐらいしかないから、火災時の避難経路としても火元に近すぎて不適。いったい、なんのための非常口なんでしょうね。次、連穴の理科準備室は鍵がかかっているから調べられない。大穴の空き教室、こちらは鍵が開いていたので入ってみたら机や椅子が山。それこそ、ここで地震が起こったらひとたまりもなく生き埋めです。あなや、学び舎の人柱。人には見せられない行為をしようと空き教室に忍び込んだ先輩が物陰に隠れているのではないかと草の根を分けるように探しました。必死の捜索にもかかわらず、いませんでしたね。脅迫の種は見つかりませんでした」
「わたしがなにしてると思ってたのよ」
えろ展開に雪崩れ込むための基本です。残念なことに現実はサブカルチャではないのでした。
顔が赤みを増すのは、告白された照れにプラスして勝手な想像への怒りと──性的行為の予感、か。
「先輩はなんだと思ったんですか? 顔が赤いですよ。猥談もO.K.な人だったんですね。意外だなあ」
ますます赤く膨らんで流行性耳下腺炎《おたふくかぜ》と伝染性紅斑《りんご病》を併発しているような顔だった。お大事に。可哀想だから、あんまりからかうのはよそう。鬼畜ルートは最後までとっておく主義である。
「手は尽くして万策尽きた、と思ってます? もう、階段を上がるしかないとか。尽くしたのは足です。状況を把握するために使うのは、足です。捜査の基本。足を使い尽くしてしまったので階段を上がることができないんですよ。もう動かない。もってまわった言い方の次は、もったいぶった言い方です。でも、そのぐらいの演出はさせてください。今からが二時間映画のラスト二〇分です。
足が尽きても頭はある、保留にしていた階段について再考します。理科室に特攻して上級生にとって今が部活の時間であることを知った僕は、先輩も部活をするために移動していたのだろうと予測することができます。そうであれば、階段を利用している可能性も濃厚になる。ただし、先輩の目的地が部活の活動場所であっても、いつ部活が終わって帰宅し始めるかわからない。行き先は順次、変わる。もしパルチザンをしているときに、ほかの教室から先輩が帰っていたら、第三棟校舎中を探し回っても見つからない。ロードローラ方式は人手をかけるからできるのであって、ひとりパルチザンごっこをしている僕にはできません。では、どうしましょうか。見つけるために、あえて探さないという手もあるのです。置かれている現状を把握し、その条件では成功が見込めないのならば、新たな条件を追加する。手はあるのです。
恐れていた先輩の帰宅、勝負の敗北条件を逆手にとって有利に進めることができる。行き先は順次変わっても、最終目的地が自分の家であることは変わらない。行ったのなら帰ってくる。僕は先輩が帰ってくるのを待つことにしました。もう、動かない。面白くもない未来を追いかける真似はしません。敬遠して機を待ちます」
ふたりで出かけてはぐれてしまったとき、相手を捜し歩くのと相手に見つけてもらうまで待つのとでは前者のほうが合流しやすい。どちらも待機していたら永遠に出会えないからだ。しかしもっとも有効なのは、はぐれそうな場所ではあらかじめ、はぐれたときに落ち合う場所を決めておくことだ。
「そういうこと。よく考えてるよね。それで、わたしには会えたの? ──会えてるじゃん。会えてるよ。やったね。そうだよね、それだけ考えたなら神様だって会わせてくれるよ。こんなに頭のいい子に育って、おねーさんうれしいよ」
おねーさんは自分より僕に感情移入していたようだ。
「思い出しましたね。僕の待ち伏せは見事に功を奏し、セカンドコンタクトを果たします。しかしそれにしても、ただ待つという行為は精神力が試されるものでした。メロスを待つセリヌンティウスの気持ちもわかろうというもの。理論を振りかざすのは簡単でも、理論は思わぬ隙間から抜け出していくのが現実です。最終下校時刻まで粘るつもりでいたのですが、もしかしたら空き教室の草の根活動中に帰っているかもしれない、もしかしたら往路と復路が違って別の階段から帰ってしまうかもしれない、と不安に駆られていました。失敗を裏付けるように、文化部の部員が続々と帰ってゆきますから。校舎にもう誰も残ってないんじゃないか、と思ったときのことです」
「女神が現れました」
「そんな感じです。誇張表現ではなく、ですよ。地獄で仏、とも言いますね。仏を追っていたらいつの間にか地獄だったんですが。だからいっそう神々しく見えたものです。後光が差していてご尊顔を拝見できないぐらい」
「きみ、もしやまた顔を見れなかったなんてオチを付ける気じゃないだろうね」
「廊下を歩く横顔は見ているので、心配には及びません。後光の照明効果担当は夕焼けです。ゆっくりと非常口の扉が開き──流石に観音開きではありませんが──光とともに現れる姿には息を呑みました。会って話をするのが当初の目的でしたが、その姿を見るだけで満足しちゃいました」
「ビーナス視点。ビーナスは部活を終え非常口から校舎に入ると、疲れきった顔で、そのせいか格好までみすぼらしく見える暗い廊下の壁を背にして座り込んだ──」
「乞食がそこにいた」
「ホントだよ。人を感知して顔を持ち上げる動作なんて、酸いばかりを噛み締めた貫禄のいぶし銀だよ。きみ、年齢を誤魔化して学校に通ってないか」
聞き上手だし、必要なところで必要な相槌をオーバリアクションでしてくれるから話がよく弾むな。反発係数が一.〇以上ある。物理法則が乱れている。
「ということで、クイズの正解は『非常口』でした。それ以外を選んだ方はお座りください。それにしても意外でしたね。抜群のプロポーションは芸術美より、機能美ということでしたか。第三棟校舎の廊下を渡ったこともあって、文化部だと信じ込んでいました。運動部であれば、文化部より帰宅が遅いということも頷けるような気もします」
「その運動部部活帰りの部員より疲労困憊してるきみはなんなんだよ。なんで部活の始まってない一年生が死にそうな顔になってるんだ。これだから戦争はダメだね」
もらったパンフレットは校舎を階ごとに輪切りにして教室を説明したもので、校舎の外は描かれていなかった。学校敷地内全体の位置関係がわかる見取り図が付いていれば、武道場も思考の範疇に入れていたのに。あんな林の中にある建物なんて、部活紹介も始まってない、体育科目でもまだ使ってない新入生にわかるか。結果的には先輩に会えたものの、完全に予想外だった。
「そんなに言うほど、酷い顔をしてました? 先輩の前だからと、気丈に耐えていたつもりでしたけど」
「顔に出やすいタイプなんだね」
先輩がそれを言うなら、誰もが顔に出やすいタイプになってしまう。なぜか。それは先輩は人の表情を読むことに非常に長けているから。わずかな所作から人の機微を感じ取る先輩は、未来を見てきたのではないかと思えることがある。なにを感じ、なにを思い、なにを考えているのか、先輩といるとそれらすべて見通されている感覚に陥ることがある。ときには、本人すら自覚していないことも言い当てる。一見、天然キャラクタのような先輩にオーバリアクションで考え事を指摘されると、驚きはかなり大きい。始めのうちは「たまたま考えていることが重なって、図星を指されたことが記憶に残っているのであって、大したことではない」と思い込もうとした。しかし、何度か同じことが起き、周囲の人間もなんとなく先輩の勘が鋭いと感じているらしいことを知ると、ただの偶然では済まない性質のように思える。
先輩を待っている間に飲んだ珈琲がなぜ二杯目だと知っているのか、その答えをまだ聞いていない。喋りすぎて喉が渇いた。ウェイトレスを呼んで、三杯目の珈琲を注文する。
「わたしは、相当な鈍感だったね。部活中もけっこうおはなししてたのに、ぜんぜん気付かなかったよ」
「気配りさんが自分への恋心に気付かないって、わりと王道ですよね」
「むむむ……。わたしは気配りさんじゃないよ。幻滅したり、傷つけるようなこと言わなかった?」
「友愛だけを捻出して、恋愛は露出しない。それが僕のプライドでしたからね。先輩がそれと知らずに接してくれることは、傷つく結果となっても成功だから喜ぶべきことです」
「それってM気質なん……感じやすい乙女心なんだね」
ほとんど言い終わってから言い直すな。しかも、わざとだ。──そろそろ、いいかな。
「わたしの緊張をほぐすために、わざと面白チックな語り口で謎解きテイストな話をしたでしょ」
「バレました? 不自然だったかな。話をして落ち着こうとしているのに、僕ばかり喋ってすみません。話をするより話を聞くほうが落ち着くかな、と思ったので」
先輩の先見術。先回りして気を回して、気配り気遣い。心配りに心遣い。気を砕いて心砕いて配って遣って尽きてしまって、心尽くし。こんなときにも発揮されてしまう性質に、僕は筋違いにも憐れみを感じた。僕の低レベルな気配りは返って翻って覆って一周して、表面上には成功している。先輩のさらなる気配りという補正によって。
気配りなんて、気付かれないようにやるものだ。先輩が気を遣わないようにと気を配って話したのに、気配りを気配りと見抜かれて、いっそう気を遣って気を遣ってないように振舞ってくれた。策を弄して裏目に出ている。
「わたしは断るのが下手です。
街角でティッシュを差し出されたら、受け取らないと相手の気分を悪くすると思って、もらわずにはいられません。にっこり笑顔まで返してしまいます。ポケットティッシュなんてほとんど使わないのに。捨てることもできなくて、机の引き出しを占拠されているにも関わらず。
ランチを食べようと入ったお店のテーブルにアンケート用紙が置いてあると、お店の人が見ているわけでもないのに、書かないといけない気分になります。答えてほしいから置いてあるのだと思うと、ボールペンを握らずにはいられません。ボールペンのインクがなかったときのためのマイボールペンがいつも鞄の中に入っています。
ナンパされたことはないです。でも、されたらと思うとぞっとしません。
執拗なセールスマンを拒めません。絶対に買わないと思っていてもマシンガンセールストークを止めることができず止まらず、相槌を求められても『はい』としか言えず、結局はこんなに一生懸命なのだから買わないと可哀想だと思って唯々諾々と契約してしまいます。電話勧誘でも同じです」
僕もぞっとしない。
気配りの話題から発展した自分語りだと思っていた。話の最後にオチがあって、それに共感して笑ったり怒ったり悲しんだりするものだと思っていた。けれど、先輩の言葉はそれ以上続かなかった。
じっと見つめられて、ようやく僕の頭が回転を始める。思考の紆余曲折を経てなんとか、話の本意を汲み取ることができた。僕に先見術の才能はないようだった。
喉を潤そうとグラスを傾けると、融解したH20の味しかしなかった。
「お返事ありがとうございました」
「どういたしまして」
異常に過剰な心配りは、随意能力ではなく不随意能力。常時発動型で、時と場所を選べない。人間とのダイレクトな意思疎通。黒く重く汚くとも、感じた途端に感じ終わっている。心を読まれる気持ち悪さなど、心を読んでしまう気持ち悪さとは比べるべくもないのだろう。超能力と呼んで差し支えないほどに超常現象化した心配りは、その能力者が先輩だったことでもつだけ不利なスキルとなった。性質が性格によって悪用を封じられ、副作用だけが残る。もとより先輩は、スキルのなにが主作用でなにが副作用なのかなんて考えていない。心配りはどこまでいっても心配り。相手を慮って、尽くす。それ以外に用途がない。尽くして尽くして尽くすことに尽きる。有利も不利もなく、善用も悪用もなく、主作用も副作用もなく、スキルがあるから行使する。先輩の先輩らしさがそこにある。
読心術ではなく心配りである以上、要望には応えなければならない。先輩は断ることができない。だから、僕が察しなければならない。僕の告白は断らないようにして断られたのだ。恋心が怨霊になりそうな失恋。
「悲しい顔をしないでください。下した決断に自信をもてなくなります。
わたしと付き合いたいと思うのなら『付き合え』としつこく言い募ればできます。マシンガンラブトークです。断ることのできないわたしはいつか折れてしまうでしょう。必ず付き合えます。わたしは告白がうれしいですし、自分自身を納得させるのにはそれほど時間がかからないはずです。あと、きみのたった一言でひっくり返ってしまうほど危うい決断なんです。だからこそ、この決断を大切にしたい。わたしのことを想ってくれるのなら、その一言を思い留めてください。わたしがきみのことを内発的に好きだと思うまでは言わないでください。わたしがきみのことを好きになれば同じことだとしても、きっかけをそんな風に作るのはやめてください。悔いが残ります。わたしにも、きみにも。誠実であればあるほど」
聞きたくなかった。その可能性を先輩に示唆してほしくなかった。行動すれば必ず報われると知っていて手が出せないもどかしさを与えてくれるな。どこかで曖昧に感じていた僕の裏側の欲望を光の下に晒すのはやめてください。ぞっとしないことをしようとしていた僕を暴かないでください。
先輩が僕を好きになる仮定に実現性がないことを知っている。先輩が僕を好きになることはない。そうでなければ、こんな形でだって僕の告白を断ることができないはずなのだ、先輩は。断れないからこそ、告白したのだから。
できるだけ公の場で告白しようとしていた。内々で処理できる個人の問題として扱ってほしくなかった。表通りからでも覗けるガラス張りのこの喫茶店は、そういった意味でとても都合がよかった。立地場所がお互いの家の中間地点だなんてのは付加価値の、僕自身への言い訳でしかない。面と向かって、きちんと言葉にして、どれだけ好きかを伝える。公的に、例外を許さないように真っ直ぐに。そうすれば、先輩は絶対に断れないとわかっていた。
「なぜでしょう? なぜ付き合えないのですか」
事務的に質問するのは卑劣なやり口だ。先輩の性格を知っていながら、性質を知っていながら、好きだといいながら僕は訊ねていた。
不満を紛らわそうとしているだけだ。フられたことへの腹いせで、うまく作用しなかった先輩の性質を詰っているだけだ。勝手に利用しようとして利用できなかったという、八つ当たりよりも酷く醜い一方的な言い分で責めている。へたくそに無感情な話しぶりを装って、薄っぺらいベールに隠された本音を探らせている。僕はなにをしているのだろう。先輩は失恋の傷心を自分の中にトレースしているのに、僕はその上ちっぽけなプライドで先輩を傷つけようとしている。
先輩は僕を見た。取り下げて、と陳情をしていた。
僕の口は容赦なかった。
「なぜ付き合えないのか、理由を聞く権利があると思います」
そんな大層な権利など僕にはない。権利はいつもお願いして得るものだ。先輩はいつも、お願いを無意識に叶えてしまっているから気付かない。
「好きな人がいるの」表情は硬い。
「それは誰ですか」間髪を入れない。
耐えるように目を伏せる。拒絶姿勢であることは誰の目にも明らかだ。
「それは誰ですか?」繰り返す。
「大真賀朱鷺」搾り出す。
先輩が人の名前を呼び捨てにするのを初めて聞いた。
「それは、恋愛感情という意味?」
「そうです」あっけなく肯定する。抵抗することを諦めている。
見知った人物名だった。平和主義というグループがあるのなら、大真賀朱鷺はその反対、戦争主義とでも呼ぶべきグループに属する人物だ。五月から部活が始まる一年生と、夏の大会で引退する三年生ではあまり接点がないが、そうでなくても積極的に関係をもちたいとは思えない人間性だった。
部活中に親しげな様子はなかったし、お似合いとも言いがたい。けれど、先輩に欠けているものを大真賀朱鷺はすべて持ち合わせている印象もある。先輩が憧れを抱くのも頷けないことではない。
「朱鷺先輩は女性です」
「変かもしれません。でも、嘘偽りのないほんとうのことです」
「女性が好きということ? つまり、内発的に女が好きなのか。それとも、男が嫌いだからなのか」
「わかりません」
深く突っ込んでも無駄だろう。しつこく訊けば必ず答えるといっても、本人にわからないことはわからない。「わかりません」が答えであって、無理に訊き出そうとすれば僕の望んだ答えを用意してしまう。
「先輩の『好きな人枠』にもうひとり入り込む余地はないのですか? 僕の入り込むことのできる場所は」
「…………」
「答えなくて結構です」
追求しない。期待を裏切らないことは、精確さが上がるということではない。むしろ、嘘を繁殖させる培養器。
「お待たせしました」
三杯目の珈琲が届いた。僕は氷を新しいグラスに移す。カラン、と澄んだ音が響いた。
そのグラスを脇に避ける。
「ごめんなさい」グラスの置かれていた場所に額をつけるとひんやり冷たい。
「僕が馬鹿でした。先輩の弱みに付け込んで意地悪なことをしました。僕はちっとも誠実じゃありません。言ってはいけない一言が、今にも口を突いて出てきてしまいそうです」
「え、ちょっと。顔を上げて」
頭を冷やすには絶好の体勢だったので、しばらくそのままでいることにした。
「それでも、ほんのわずかに残された良心が疼きます。自分の行動を後悔しています。
お願いできる立場でないことはわかっています。これは僕の願望です。先輩が合わせる必要はありませんし、ましてや従わせようなんて考えていません。つまらない独り言です。シカトすればそれで済みます。
僕と先輩の関係をここで会う前に戻したいです」
人生のリセットスイッチはある。ただしそれは核ミサイルのスイッチのようなもので、みだりに押すことができない。もし押すときには手順を踏まなければならず、その手順とは相手と自分が「一、二の、三」で同時にスイッチを押さなければならない、というものだ。少しでもタイミングがズレるとスイッチが爆発する。ちゅどーん。
「わたしもです。だから、顔を上げてよ。恥ずかしいよ」
わたわたしているのが顔を上げなくてもわかる。そんなオーバリアクションだからよけいに人目を集めるのだと気付いていない。
僕は謝罪しているはずなのに、なぜか先輩を虐めているような気分になってきた。
「先輩なんて嫌いです」
やっぱりわたわたしている。僕が顔を上げたことで安堵して、僕の言葉を聞いて落ち込んで、何回か頭の中で反芻してから微苦笑した。
「ごめんなさい。わたしが優柔不断だからこんなことになるんです」
「先輩」
唐突に呼びかけられてきょとんとしている。
「ここでの僕たちをリセットする前に、なぜ先輩が来たとき僕の珈琲がお替わりしたものだとわかったのか教えてください」
先輩は「それ」と言って、避けられたグラスを指差す。
「あのときはなにも入っていませんでしたよ?」
ストローが二本刺さっていたわけでもない。ブラック派だから砂糖もミルクもシロップも入れない。
「きみは冬でもアイスコーヒーだよね。『なにも入ってなかった』って言うけど、氷は入ってたよ。キンキンに冷えたのが好きなのかな。お替わりをもらうと、古いほうのグラスから残った氷を移し替えるよね。移し替えた氷は少し溶けていて、大きさが違う」
グラスを見ると、確かにその通りになっていた。三杯目のこのグラスは、上から順に中小大の氷が並んでいる。二杯目の時点でなら、大きい氷の上に小さな氷が乗っていただろう。
「氷。熱血とか、熱中とか、人の温かみだとか、そういうことを避けているような態度だった。ファーストコンタクトは意識していなかったけど、ファーストインプレッションは強く印象に残ってる。きみは氷。人との関わり合いをしないわけじゃないけど、どこか冷めた視点で物事を見てた。なんとなくわかるんだよ、そういうのって。だから、今日の告白はうれしかった」
「おねーさんはうれしいよ」か。とことん弟だな、僕は。最初っから、男として見られていない。そう宣言されていたではないか。
「一、二の、三。ちゅどーん」
滅茶苦茶なタイミングでスイッチを押して僕は自爆した。リセットなんかしない。さっさと進めないといけないのに、やり直している時間はない。いつまでも弟ではいられない。
先輩は九〇度に近い角度まで首を傾げている。
「行きますよ、先輩。ここは僕が奢りますからね。って先輩、なにも頼んでないじゃないですか。なにやってるんですか。息を切らして来てたんですから、飲み物ぐらい頼んでくださいよ」
「ヤだよ。わたしに奢ろうなんて百年早いわ!」
厄介な相手を好きになったと、僕はようやく気付いた。
薄暗がりの部屋で喘いだ。
言葉にならない、獣じみた声だった。感情が迸る、制御不能の音だった。僕は泣いていた。
息が絶え絶えになっていて荒い。押し殺すように泣く僕を、僕の意識が見ている。陰惨で陰鬱な姿だった。正視できない。
「目、赤いよね」
気が付く。雲間から太陽が現れると空一面を覆っていた暗雲が背景に成り代わってしまうように、感覚は現実を捉えて幻想を見失ってしまった。
「眠いんです」
「目ぇ開けて寝てたのかよー」
いつも通りの日常が待っていた。どういうわけか、変わらない関係を保っている。修復不可能なほどに破壊してしまったのに、奇跡か悪夢のように不変であり続けた。
退屈だが、これといって不満のない生活。両親は健在で共働き、当たり前のように当たり前に学費を出してもらっている。学校の成績はまずまずで、交友関係もとくに支障はない。授業が終われば、片想いしている一年上の先輩たちと部活に励む。
そんな日常を嫌って、僕は意を決し先輩に告白するも、恋破れる。錯乱した情けない僕はあろうことか先輩をバッシングした──それなのに僕はのうのうと、映画のフィルムのように変わらない毎日の一コマを演じている。ここまで前回のあらすじ。
「そろそろ部活終わり!」
武道場を見渡すと、僕たちふたりしかいない。いつのまにか、放送室から帰宅を促す童謡が流れていた。
先輩は告白など意に介していないかのように僕と接した。実際、先輩にとっては大したことではないのかもしれない。忘れてほしいと言ったのは僕だが、本当に忘れることなどできるのか。無視している、というわけでもなさそうなのが気にかかる。健忘症のように、ぽっかりと記憶がなくなっているのだろうか。あまりに自然で、僕の記憶こそ夢だったのかと疑い始めなければならなかった。
「また寝てる? おーい、起きろー。夜になるぞー」
あの日、待ち合わせ場所に現れたときのように、大きな手振りで僕の注意を引く。そんなことしなくても、僕はいつも先輩を見ていた。
「ひとりで部活してたのですか?」
先輩の頭が傾く。てんてんてん、と空中に三点リーダが浮かぶ。
「いつから寝てんだ、きみは。いっしょに組み手して、型をやったじゃないか。『やめ』の号令をかけても型の姿勢を崩さないから、まじまじと見つめていたんだが、それでも身じろぎひとつしないから泣く泣く声をかけた」
泣く泣く?
「いつもとは打って変わって攻勢に出るから感心していたんだが、寝たまま組み手してたのか。意識がないほうが強いのか。酔拳ならぬ睡眠拳か」
その駄洒落はさほどうまくない。
「いつも何時に寝てるんだ。熱はないか。身体はだるくないか。なにか薬を摂ってるのか。息苦しいことはないか。脈は正常か。うんちは柔らかくないか。不調を感じる部位はないか。きみが心配だ。同伴してあげるから、お家に帰ろう」
背中を押されて帰宅準備にとりかかる。僕が不調なのは、先輩の態度が不変で考えていることがわからないからだ。
着替えをしようと入った部室で鼻が悲鳴を上げた。いつものことだが。いつもとはちがう異臭がした。窓の錠を解いて新鮮な空気を手繰り寄せるも、臭気は床に澱んでいるらしく、高い位置にある窓では開けても効果が薄かった。換気の基本は風の通り道をふたつ作ること。入口と出口を設けてやれば吹き溜まることなく通り抜けてゆく。しかし部室に窓はひとつしかない。これから着替えをしようというのに、先輩を道場に待たせたまま戸を開け放っておくわけにもいかない。
部員が少ないために、部室はひとつしか割り当てられていない。男女とも同じ部屋で、男子の次に女子が着替える手筈になっている。女子が着替えている最中には、それとわかるように戸に札がかけられる。男子が入らないようにとの配慮だが、それはそれで不穏な気もする。深くは考えないでおこう。
手早く着替えを済ました。と、なぜかハイタッチを求められたので合わせる。「イェイ」
先輩は入室するときに札をかけなかった。先輩がかけない札を僕がかけることもないだろう。短時間だし、僕以外には誰もいない。部屋の前に僕が立っているから安心しているのだろうか。しかし、信頼しすぎではないか。僕は先輩が好きだ。だからこそ起こりうる、最悪の事態というものがある。先輩はもっと警戒すべきだ。自分で言うのもおかしな話だが、僕という人間は信用ならない。
あるいは。この場面で札をかける行為は、先輩が僕を拒絶する構図になってしまうために避けたのかもしれない。傷付けないための心配り。
僕はフられたが、断られていない。僕が忘れようとしている以上に、先輩が忘れようとしているのかもしれない。告白を承諾することも拒否することもせず、告白された事実を受け入れることもしない。決断なんて格好いいことを言いながら、していない。些細なことに気付いて傷付かないように気遣うのは、誰のためか。
僕たちは反射した自分の像を見ている。
鈍い重みのある落下音がした。部室の中。それ以外の音はなにも聞こえない。その一瞬、宇宙にいるかのように無音だった。
逡巡せずに戸を開く。正直なところ、役得と喜ばないこともなかった。しかしそれは開けてしまってからの感慨であって、僕の行動原理は不純な感情がもたらしたものではなく防衛本能からだった。先輩の存在はかけがえのないものとして僕の人生に組み込まれている。失えない。僕の好きな人、だ。
腰を抜かしたからくり人形が振り返る。かたかたかた。虚ろな目が僕を見とめて、先輩は床のショルダバッグを閉じようとする。しかし、手が滑って目的を果たせない。
「なにを隠している」
震える自分の手を見て、先輩は考えあぐねている。
「いくら先輩後輩だからって、その前に男女なんだし、女の子の着替えを覗いちゃダメだぞっ……」
語尾が震えているのは無理もない。青い唇が震えているのだから。早口でまくし立てるから、言ってることが支離滅裂だ。道着のままで、帯が緩んですらいない。とりあえず、「朱鷺先輩の着替え、見放題だったよね」とツッコめばいいのか。
「僕にくらい、もう少し心を開いてくれてもいいでしょう。見せてください」手首を掴む。
完全にお人形さんになってしまう。微動だにしない。やがて腹話術人形になって顎がガコンと下がり開いた口から空気が漏れて、
「あ、……ああ、……あああ、……ああ、ああ……あ、あ、あ、あああああああああぁ!」抱きつかれる。
「せ、先輩?」
「と……き。と……き。と、き。とき……ねえ、とき……とき? ……もう、イヤだヤだヤだヤだヤだ」
ヤだ、だって? 先輩が拒絶した。単純明快な拒否反応を、先輩がした。決壊している。──僕は理解した。
とき。時? いや、朱鷺だろう。支えになれるのなら代理で構わない。子供のようにすがる先輩にかけるべき言葉は間違いの訂正では、決してない。背中をさすり、嗚咽を漏らす先輩にハンカチ代わりのブレザーを提供するだけだ。形而下では嬉しいが、形而上ではやはりわずかばかり虚しさが込み上げる。
落下音は尻餅をついた音だろう。着替えをしていないことが重症を物語る。着替えにはまったく手がついていない。着替えようとバッグを開けたら見知らぬ異様な物品が挿入されていて、それを見た途端に緊張で身体が硬直した。立っているうちに脚の筋肉が弛緩し、手を付くこともできないまま尻餅をつく。推測が正しければ、先輩は入室してから尻餅をつくまでの数分間、ずっと立ち尽くしていたことになる。
「バッグを開けますよ。いいですね?」
腕に抱きついている先輩は頭の動きだけで意思を表す。小さな肯定。先輩を人形にしたのは手紙でも写真でもなかった。
バッグにはブレザーの制服がきれいに畳んでしまわれていた。育ち柄のよさが表れている。白濁の粘液など、嘘のようだった。
異様な物品。
異臭の正体。
白濁の粘液。
男性の精液。
リボンからブラウス、ブレザー、スカートまでまんべんなくべったりどろりとデコレーションするように精液がかけられている。
思考に去来するのは、僕ではなく先輩がどう受け止め、どう処理するのか、ということ。他人に嫌な思いをさせないために気を配る先輩。相手に嫌な思いをさせないためならば自分が嫌な思いをすることにも堪えられる。相手に嫌な思いをさせるくらいなら率先して嫌な思いをしてしまう。嫌悪することに嫌悪する。嫌悪されることに嫌悪する。それはつまり、自分に対して嫌悪感をもたれることを最も恐れているから。先輩はおそらく、自分のされたことを明るみに出さない。たとえ僕にだって、言われなければ事実を隠していた。犯人を糾弾することなく、泣き寝入りする。悪意を向けられたのは自分の至らないせいだと己を責めるのだろう。僕にできることは。大真賀朱鷺・ハンカチの次は、僕はなにになったら先輩を救える?
「先輩、先輩は男装も似合うと思います」
一か八か、危険な賭けだったことは否めない。だが朱鷺先輩の投影が残っている僕ならば、弟的存在の僕ならば可能だと思った。今だけは、男として見てくれなくて構わない。
着たばかりのブレザーを脱いで、先輩に渡す。ブラウスの代わりのカッタシャツ。スカートの代わりにズボン。先輩が部室で着替えている隙に、穢れたブレザーは焼却炉で燃した。先輩がもっていたら、洗濯をしてまた着てしまいそうだったから。そんなこと、僕が我慢できない。
ブレザーを貸し与えることによって明らかになった非常に辛い事実があります。先輩が着ると丈が短い。僕は悲しかった。
「先輩先輩。先輩が僕のブレザーを着て歩いてるのってなんかこう、胸がむぞむぞします。抱きついていいですか?」
僕のクールなアイデンティティが崩壊してでも、いつもの先輩の表情をとり戻したかった。その成果として、はにかんだ顔で抱きしめられた。またも僕は気を遣ったつもりで遣われている。成長していない。でも、これでいい。今は、まだ。
同伴してくれるはずだった先輩に同伴して、帰途の道に着く。先輩は上の空で気付いていないが、僕たちは通行人の目を引いていた。普段は凛としているだろう少女が物憂げな眼差しで、そしてなぜか男物のブレザーを着ているというのは、見るものをドラマティックな妄想に掻き立てるのだろう。ちっちゃい道着少年が先導しているのは小道具の一環だ。
「確認しておきます」
先輩は俯いていた顔を上げる。
「犯人を追及するつもりがない」
こくん、と首を縦に振る。
「報復するなんて考えられない」
躊躇いなく頷く。
「反省を促すこともない」
溜息を吐くような首肯。
「憎いとさえ思わない」
うなだれるような頷き。
「嫌われるようなことをした自分が悪い」
諾い、肯んじる。
「理由だけわかればいい」
頭は動かさず、目で頷く。
「理由がわかったら、今後は気を付ける」
感心したように僕を見ている。
「その考え方ってどうですか。悪いのはぜんぶ自分のせいだと抱え込んで押さえ込んで、いつもいつも相手に合わせて同調して同情して、まるでサンプルの烙印が押されているかのように典型的ないい人で、人間なのに感情がないみたいに感情を殺して感情を隠して感情を欺いて、自分なんてものがなくて空っぽなのに外側からは見栄えがいい。そんな考え方のままでいいんですか」
ぱちくり、なんて効果音が聞こえてきそうなまばたきをひとつして立ち止まり、僕を見ている。
「先輩の真似です。僕だって、伊達で告白したわけじゃありません」
駆けてきて、輝くような笑顔で抱きつかれた。ボディランゲージがオーバだとは思っていたが、スキンシップはこんなにオーバな人ではなかったはず。人恋しさと人間不信は紙一重だ。
支え合いの象形文字『人』というよりは、片方だけが踏ん張るカタカナの『ト』の字になって先輩を家まで送り届けた。縦棒より二画目のほうが長いから余計にバランスが悪い。
さて、と。
僕は騎士《ナイト》ではない。主君のために命を捧げ剣に誓い礼に堅く勇を尊び智を慈しむ、誠実で実直で直情の優れた人格を有した、忠誠心あふれる人間では残念ながらない。言動はすべて自分のためであり、自分のためになることしかしない。だからこれは、私怨だ。被害者になることのできない先輩からは切り離された、正義とは無関係に発生する憎悪。もしこれが先輩のためを想っての行動のように見えたとしても、それは先輩に好かれるための打算的な動機によるものだ。
高跳び。犯罪を起こした人間がその周辺から立ち去ること。特に、海外に逃走する場合を指すことが多い。間違っても陸上競技ではない。高跳びについて、僕はこんなことを考えたことがある。どうせ帰ってこないのならば、最初から異国の地で事件を起こして住み慣れた街を高跳び先に選べばいいのではないか。一瞬で終わる犯罪の実行時間こそ見知らぬ遠隔地で過ごすほうが理に適っている。足取りを残さないように気を付ければ、容疑者に上がることもないだろう。疑われたとしても、旅行者は捕まえにくいはずだ。
しかしそれは、犯罪心理学的に考えると現実的ではないらしい。土地勘のない場所では計画を立てにくく、とっさの機転が利かないので一度でも計画が崩れると建て直しが効かない。第一、不慣れな地では物事の輪郭が精確に得られないために保守的な意見を採用しやすい。計画的な事件も衝動的な事件も起こしにくいといえる。旅行者が容疑に上がらないのは、統計的に犯罪を起こすことが少ないのも理由のひとつだろう。
部室で起こった事件は、だから武道場で活動している部の所属者──なかんずく、部内の人間が起こしたものだと目算を立てている。別角度からの見地でも傍証があるのだ。部室は道場とをつなぐ戸しか出入り口がない。窓は風の通り道であって人間の通り道ではない。無理とは言わないが、それは無理にならば通れるということだ。僕たちが道場で部活をしていれば誰が部室に入ったのか必然的にわかるし、部外者が入室しようとすれば目に付く。最後まで武道場に残っていたのが僕と先輩だったのは犯人を絞る上で難点かもしれない。僕はトリップしていたし、先輩は犯人を追及する気がない。言動からしておそらくそんなことはないだろうけど、先輩が犯人の目星を付けていたとしても僕に教えてくれないだろう。僕が『お願い』でもしない限り。でも犯人の立場で考えてみれば、目撃者が僕や先輩であろうとも、それ以外の人間であろうとも等しく回避すべきリスクだ。先輩の性質は操縦可能なほど異端としては知られておらず、その兆候もことさら風評されているわけではない。度の過ぎたお人よし、その程度。僕の空白期間も、組み手をしていた先輩にだってそうと気付かれなかったぐらいなので犯人だって僕に見られることを避けるだろう。
学校指定の販売店でブレザーを購入する。店番の老婆が女生徒用のブレザーを買う道着少年に訝しげな眼差しを向けるが、それには構っていられない。サイズは処分するときに確認している。
我が部の部員は九人。顧問はほとんど幽霊顧問で、来ていれば物珍しさで目立つ。だから彼女は除外。さぁ、と言うところで挫ける。なんだって僕は進んで身内を犯人に仕立て上げようとするのか。場慣れしているから。部室に入っても気に留められないから。あの、おぞましくも軽率な行為は場慣れなんて必要な大事業だっただろうか。それに、常に誰かが部室の扉を監視していたわけでもない。見逃すこともあるだろう。犯人に仕立て上げるべきは部外の、文字通り部外者。そう、間違いなく。そうでなければならない。
出入り口としては認識されていないが、それが可能な窓が部室と武道場外部とを繋げている。武道場の周りはサクラが植えられていて、見通しが悪く人気もない。窓から侵入し、先輩のブレザーに浴びせかけてから来た道を引き返すことはたやすい。でも、窓から侵入するとしても問題が残っている。昂ぶるまでの時間、その間に誰かが入室したとき言い訳ができない。日常的に着替えに利用されている部室とはいえ、下腹部を露出させていることの弁明はできない。部室の家具といえば壁に備え付けられた棚があるぐらいで、隠れる場所はない。当然、部室に鍵はかからない。そんなものがあったら女子の着替え中に『通り抜けしないでください』の看板にも似た、相手に狙いどころを教える間抜けな札をかける道理がないのだ。
見つからないための解決策はある。『手早く済ます』、もっとも基本的なことだ。そのために必要なことといえば、精液をあらかじめ用意しておくだけ。たったそれだけで見つかりにくくなる上、犯人の輪郭を広げることができる。性別だ。用意しておくのなら、容疑者を男性に絞る必要がない。先輩のもうひとつ特筆すべき性質、同性愛者であることはどの程度みなに知れているのだろう。喫茶店で告白したあの日、僕は初めて知った。それまで知らなかったからといって、ほかの誰も知らないとは言わない。女子であれば知っていて当たり前の、公然の秘密なのかもしれない。もし仮にそうなのであれば、行為にも意味が生まれてくる。事実は必ずしもその通りではないようだが、先輩の同性愛を男嫌いと解釈することはなまじ無茶なことではない。悪意の表れに、男のシンボルたる精液を振り撒くことは理解できずとも納得はできる。
もしかすると、部室に侵入する必要すらなかったのかもしれない。先輩のバッグは窓の真下にあった。犯人は精液を所持し侵入するつもりで部室の裏手に回ったが、目当てのバッグがすぐそこにあることを幸いに手を伸ばしただけで行為に及んだことも考えられる。窓のサッシを調べて外部犯か見当を立ててみようとも思ったが、それも当てが外れた。入室していないのなら高飛びから推察した心理的な障碍も低い。
犯人の経路も手順も蓋然性の高さに確立されているのに、容疑者の幅はほとんど無限に広がった。それは僕にとって、願ったり叶ったりの結果だった。
本日二度目の先輩宅。これまで何度か来たことがあるが、実はまだ足を踏み入れたことがなかった。
呼び鈴を鳴らしても返事がないので「せんぱーい」と呼びかけながら玄関扉に手をかけるなり急に開いて腕がぬっと伸びてくるかと思えば肩をつかまれ引き込まれると同時に形のよい握り拳が玄関扉から外に排出されて僕の腹部と衝突を果たした。
玄関扉の向こうに見えるもの、それは無表情の中でわずかに口端を吊り上げる朱鷺先輩だった。左手で引き寄せ、右手で殴る。衝撃二倍のプッシュプル。死ぬより痛い。
「あれ、どうしたの。そんなお腹抱えて。きみ、ウチに来ていきなり大爆笑かよ。ウチにゃそんな可笑しなものはないぞ」
奥からやってきた先輩は、声を殺し涙を溜め腹をさする僕の姿を見て間違ったリアクションをとった。もしそんな大爆笑の種があったとしても朱鷺先輩の前では笑えない。朱鷺先輩の前で笑うときは、そうでもしないと狂気に侵されそうなときと侵されてしまった後だけだ。
朱鷺先輩は「やれやれ」とでもいうように首を振って見下している。僕の扱い、おかしいですよね。
「部屋に上がってよ。玄関の立ち話もなんだしさ。なにがそんなに面白かったのかちゃんと説明してよね」
たたたっ、と階段を上がっていってしまう。
「朱鷺先輩、いつから来てたんですか?」
「早く行って話してやれ。面白いことがあったんだろ?」
事実が変更されている。先輩のお宅を訪問したら朱鷺先輩が出迎えてくれて、そのときちょうどユーモラスなものを発見したので僕は笑いました。とても楽しかったです。またみんなでハワイに行きたいです。嘘日記。
先輩と朱鷺先輩と僕。好きな子の部屋に初めて上がるというのに、ときめきとはまったく別種の緊張感を漲らせていなくてはならない。告白前の僕では予想できない展開だ。実力ではとうてい朱鷺先輩に及ばないし、実力が凌いでいたとしても揮わない。僕はフェミニストではないけれど、世界は男女不平等なのだから。覚悟しよう、もう一発や二発は甘んじて受ける。それが心身ともに機能停止する状態に陥ったとしても。お寺の鐘が僕の頭に移植され、未だにぐわんぐわんと鳴り続けているとしても。
「飲み物、新しく用意するね。先輩はジョルジで、きみは?」
「普通のお茶でいいです」
「普通のお茶ってなんだよ。『なんでもいい』なんて名前の料理はないんだぞ。見繕ってくるけれどもさ」
整然の中に混じった雑然。潔癖すぎるよりも安心できる。暖色を基調としていて、ふんわりやんわりとした感触がある。きゃぴきゃぴとは違うが、女の子らしい部屋と形容できるだろう。先輩の空気を感じる。先輩のいい匂いがする。いけない、ここでくんくん嗅いだら本当に変態だ。
ビーンズテーブルを前にして正座する僕と、布団を潰してベッドに腰掛ける朱鷺先輩。常連は年季の入り方が違う。
「それはブレザーか」
ブティック上新と印字されたビニル袋。名前負けするにも程がある。
「そうです。渡すために来ました」
はて、部屋に招く頻度が親密度を示し、僕と朱鷺先輩とでは歴然と差が開いてしまうのはこの際とかく言うつもりはないが、それを朱鷺先輩はどう受け止めているのだろう。先輩は気持ちを打ち明けているのだろうか。
「朱鷺先輩はなぜ来たのですか?」
「教える義理はない」
核シェルタのようだった。中に核兵器が設置されている核シェルタなんて聞いたことがない。
「なぜ僕は暴力を揮われたのですか? これは教えてもらっても文句ないと思いますが」
「それを言われたいのか」
物理的な痛みを伴う視線がざくざくと刺さる。目からビームが出ているのではないか。
「もうおはなし始めてるの? おいてけぼりにしないでよね。
先輩たちって仲あんまし良くないと思ってたけど、いらぬ心配でございましたわね。嫉妬しちゃうわぁ」お盆を持った先輩が器用にドアを閉める。
その嫉妬は誰に対するものなのか、それが僕だということを僕は知っている。朱鷺先輩と仲良く談笑していることになっている僕。朱鷺先輩は、その嫉妬が誰に向けられたものか知っているのだろうか。
「いや、玄関で迎えるなり朱鷺先輩が面白い話をしてくれたので、あまりの可笑しさに笑いを堪えきれなくて。いま玄関での続きを急かしていたところです。朱鷺先輩、森の動物たちはその後どうしたんですか」
芸人殺しのキラーパス。殺されたら殺し返す。僕は紳士だから女性を殴ったりはしない。
朱鷺先輩が遊びに来て、浮かれている先輩にとって事実が事実として機能しないのならば、僕だって虚言を弄して都合よく既成事実化してしまう。あとのしっぺ返しは怖いから考えない。
「国と国の間にある、領国の知れない静かな森にウサギとキツネとシカが棲んでいた。ウサギは極端なペシミストでいつもいつもいつも朝も昼も晩も途切れることなく途絶えることなく泣いていた。その日は泉に映った自分の姿が醜く揺れているのを見て泣いていた。キツネは面白がって囃したて、波紋を立ててはさらに水面を歪ませてからかった。シカはシカトしていた。ある日、汚い臭い気持ち悪いの3Kを備えた男が森にやってきて、三匹に『すまんが寝床を分けておくれ』と嘆願した。ウサギは男のために寝床を作ってやるばかりか食事の用意まで甲斐甲斐しく世話をした。キツネは遠巻きに半目で鼻を摘まみながら同じく客人であるかのようにもてなしを受けつつ男の話を聞き、その合間にウサギの仕事にちょっかいを出していた。シカはシカトしていた。そうして数日が経ったとき、『実は、儂は魔法使いだったのだ。そろそろ儂は次の地へ赴かねばならない。世話になったお礼にお前たちの願いを叶えてやろう』と格好よく気品の漂う綺麗な男性が仰いました。瞬時に近巻きで全目で鼻の穴を広げたキツネは、しかし考え込んだ。『仮に吾輩が無病息災不老長寿を叶えども、ウサ公が『怨敵野干に滅びあれ』と祈願しすれば吾が願いは水泡に帰す。ウサ公シカ公に本懐を遂げさせ、後に吾輩が本懐を相殺する願いを聞き届けてもらわば好し。急いてはことを仕損ずる、後手に回りて果報を待て』と結論に至る。ウサギは魔法使いに願いを耳打ちした。それを境にウサギの姿は森から消えた。シカはしかとシカトした。いつまで経っても願いを打ち明ける様子がないのでキツネは痺れを切らし、それ以上に魔法使いが痺れを切らしたので森を出発してしまった。終。お話のお相手は仔猫ねこでした。それでは御機嫌よう」
……いや、面白かったけども。けどもさ。
ティーカップの載ったトレイを持った先輩は立ったまま固まっている。朱鷺先輩はベッドから腰を上げ、オブジェと化した先輩の手元からティーカップを取り、香りを愉しんでいる。
解釈の余地がいくつもありそうな話をアドリブで思いつくのか。『森の動物たち』という枕もろともキラーパスを受け止めやがった。そのまま三点シュートを決められた気分だ。ナイスアシスト僕。
なにが驚くといって、朱鷺先輩がこんな長台詞を喋ることに驚きだ。地区大会の試合前、部長から部員へ長々と延々と激励の言葉を述べたのに対し、副部長だった朱鷺先輩は「勝て」の一言だけだった。一言だけでも、試合前に朱鷺先輩が喋るのは珍しい。その喝のせいかどうかはわからないが、いつも一回戦敗退を喫する我が校がその大会では成績上位を独占した。当然のごとく、朱鷺先輩は女子の部優勝を果たす。そのときの地方紙のインタビュに朱鷺先輩は「勝とうと思った」と言い残している。編集されたのではなく、本当にそれだけしか言わなかった。さすがに県大会は気合だけで勝てるものではないらしく、我が校はボロ負けして束の間の栄光も地に堕ちたが、朱鷺先輩だけは本来ならば勝てたのではないかと思っている。地区大会で朱鷺先輩が見せた動きは当時レギュラ入りできない僕の目にも地区大会レベル・県大会レベルなんてものではなく超高校生レベルだとはっきり感じた。勝たなかったのは、勝とうと思わなかったから。
童話のような、森の動物たちのお話。それは同時に、寓話でもあるのではないか。誰彼のあれこれを下敷きにした話、そうでもなければ即興で作れるものか。そう考えてみれば、先輩はウサギのような気がするし、シカの底知れなさは朱鷺先輩に重なる。となれば、残った人物と余った配役で僕=キツネとなってしまうが、不承不承それを認めよう。寓話だと感じさせるに至ったのはなにより魔法使いの存在。これは人物を当て込むのではなく、先輩の性質そのもの。周囲の期待に応え続ける先輩にこれ以上のハマり役はない──のだろうか。比喩ならば預言書のように暗示的。恣意的判断なしでは読解できない。朱鷺先輩にしてみれば出来心に出て来たお話。出任せの出たとこ任せ。深読みするほうが馬鹿みたいなお話なのかもしれない。
「なんだか怖いね。結局、願いを叶えてもらったのはウサギだけ。ウサギはなにをお願いしたんだろう」
ステータス異常:石化の解けた先輩は僕の正面に座っている。テーブルが小さいから近い。
「ペシミストの先輩こそ誰より理解できるんじゃないですか?」
「え、わたし? ペシミスト?」
「基本的にそうでしょう。世の中の悪いものはぜんぶ自分のせいだと一手に引き受けてしまう。それをペシミストではないとでも?」
「そうかなあ。でもわたし、それで悲しんでるわけじゃないよ。自分が悪いんだったら直すことができるもの。傲慢かもしれないけど。だからわたしはどちらかというとペシミストの反対の……なんだっけ?」
「楽天家と言いたいならオプチミスト。ペシミストには悲観論者のほかに厭世家の意味がある。今のこいつは世を愁いてもいないし儚んでもいない。ペシミストだという観察は誤っている」
女の子の部屋で女ふたりと男が討論して勝てるとは思わない。身の程ぐらい弁えている。女の子を相手にすると怖いよ。女の子でなくたって朱鷺先輩は怖いんだから。
「僕はウサギが消えたことより、なんでも願いを叶えることのできる魔法使いの存在が怖いです」
「そんなこと言ったら幻想文学を読めないよ」
「ストーリラインの機軸として魔法使いを捉えるのなら、それが物語内登場人物に姿を晒し声を聞かせることがまず恐怖だと思うんですけど」
「うーん、きみはリアリストだね」頬を膨らせる。
奇跡を信じるには現実はあまりに過酷で痛烈だ。だからこそ幻想を、という人間もいるがそれは逃げであり負けだ。そして僕だ。
「仔猫ねこさんはどう思います?」先輩は紡ぎ手に水を向けた。
その話の振り、朱鷺先輩でなければ墓穴を掘ったら入りたい気分にさせるぞ。僕のキラーパス以上に殺傷力が高い。用法・用量を守って正しくお使いくださいね。
「今の会話、リアリストを哲学用語として聞くと根底から矛盾していて面白い」
ちげーよ。なんで先輩と僕のアットホームな会話に冷静な見解を述べてんだよ。
浮かれた先輩と最初から感性がズレれている朱鷺先輩、この部屋に変な場が形成されてはいないだろうか。相手が相手なだけに心中でツッコみを入れることしかできない不甲斐ない僕を許して欲しい。
「そういえば。面白かったけど可笑しくはなったよね。なんで笑ってたの?」
そう来たか。枕さえ完璧に受けつつ面白い話を語ってみせてくれたが、爆笑を促すような面白さではない。できなかったのではなく、あえてしなかったのだろう。そのことに気付かせないまま、忘れた頃に「面白い」とキーワードを紛れ込ませた会話を交わし先輩に思い出させる。間接的な不意打ち。報復のキラーパス。
このままでは、感性がズレているのは僕ということにされてしまう。異様に笑いの沸点が低い人間、「シカはシカトしていた」などで爆笑したと思われては人間の尊厳を手放すことになる。
「どしたの? もしかして前座のおはなしがあったの? ちゃんと教えてよ」
僕にあの話のプロローグを即興で作る能力はない。しかも、爆笑するほど面白くなんて臍で茶を沸かすように無茶だ。
神妙に『普通のお茶』を飲む振りをして時間を稼ぐ。朱鷺先輩の創作童話の中で爆笑したことにはできない。だからといって爆笑するような話を自分で作ることもできない。どうするか。そもそも、殴られて腹を押さえているのを爆笑して腹を抱えたのだと勘違いすることが思いも寄らないキラーパスだ。パス回しは、最初に回してくれた人にお返ししてしまえ。
氷が大量に投入されている湯飲みから口を離し、息を整えたところで、
「そろそろ返してやれ」
むせてしまった。「え、パス?」最近は朱鷺先輩まで僕の心裡を読むことができるのか。
「ブレザー。そのために来たんだろ」
気圧を感じ取る器官が敏感になる。先ほどブレザーが話題に上がったときは先輩は席を外していた。なぜ今まで空気の中で生活できていたのだろうと疑問に感じるほど、空気が重い。僕たちは大気の上に浮かんでいるべきだ。
先輩は固まった。さっきのようにただ硬直しているのとは違い、凍結している。だがそれも、一瞬で溶解した。
「洗ってきてくれたの? ありがとう」
溶かしたのは、大真賀朱鷺の存在。悔しいが、それは紛れもない事実だ。この部屋のこの場は、先輩と朱鷺先輩によって形成されている。僕ひとりがお客さんだ。僕ひとりが呑まれている。隣の朱鷺はよく客食う朱鷺なので要注意だ。
ブレザーを処分したことは伝えていない。先輩なら洗濯して着てしまう、という予想は当たったわけだ。それにしても。朱鷺先輩が「返してやれ」と言ったにせよ、洗濯しようとこんな短時間では乾くはずなく、皺ひとつない、販売店のビニルに包装されたブレザーを見て「洗ってきてくれたの?」と言えるのは、単に今の先輩が浮かれているだけではないのだろう。自分のために僕が新品のブレザーを買うという発想が一切ないからだ。自己評価がとにかく低い。
「教えろよ」
カップから上がった視線がククリのように鋭利だ。
「なにがあった?」
人間の目では絶対不可能なはずの、猫のように──否、蛇のように虹彩が引き絞られてゆく縦長の瞳。なんだ、これ。逃げ出したい。でも身体が動かない。睨まれた蛙になってしまった。
「どこまで、知っていますか?」
「こいつの身になにかが起きたことは態度でわかる。なにが起きたのかは知らない」
そういえば、朱鷺先輩は先輩を「こいつ」と呼んでいる。この部屋内で二回目だ。学校の部活中は名字で呼んでいたのに。関係が違うのか、変わったのか。
朱鷺先輩は先輩の態度から事態を推し量っただけで、具体的なできごとはまったく知らない。相談することすらないままに、存在だけであの凍結は一瞬にして温め溶けたのか。ほんの一時間前の、僕といたときとはまったく別人のように浮かれきった先輩。安心感、全幅の信頼。格の差を見せ付けられた。
「だが、見当は付く。洗ったという言葉が使われたのは汚れたからだ。ブレザーが切り刻まれたわけではない。ブレザーが汚れたにもかかわらず、こいつ自身は汚れていない。シャワーを浴びる時間もない。ブレザーを脱いでいるときになにかをされている。そんな場面は部活で道着に着替えているとき以外に考えられない。部活中にあったことを話せ」
睨む蛇の目は、先輩のためにしているのですね。僕が先輩の危機を僕自身の危機と同じように感じるのに似て、それ以上に、朱鷺先輩にとっての先輩は同体であるかのように近い。先輩が感じない害意を敵意を戦意を朱鷺先輩が探り、先輩に欠けている嫌悪を厭悪を憎悪を朱鷺先輩が補う。さながら騎士《ナイト》だ。朱鷺先輩は僕なぞとは比較にならないほどナイトしている。
先輩の顔を窺う。先輩の口から言わせるわけにはいかないが、かといって僕が言ってしまっていいのだろうか。
迷っているうちに、
「スペルマ」
と、先輩が言った。
少なからず驚く。先輩にそんなボキャブラリがあるとは、まさかの英語。いや、頭の悪そうな俗称を口にするとは思わないが。しかし先輩が性的表現を曖昧にせず明言してしまうとは意外だった。
「で、そいつはどうなった?」犯人のことを言っているのだろう。
先輩の細い指先がブティック上新からゆっくりと上昇する。まるでこっくりさんでもするように、先輩も驚いたような表情で動く自分の指先を見ている。僕の目も、綺麗な指を追う。動きはちょうど、僕の鼻先で止まった。目が合う。
「え、それ。片付けをしたって意味で犯人じゃ──」「停まらなかった」
その言葉通り、ダンプカーにでも轢かれたような衝撃が身体中を巡る。ブレーキが利かなくても、ハンドルをきることはできたに違いない。推定無罪の精神を取り入れてはいかがでしょうか。
いつの間にか立ち上がり迫っていた朱鷺先輩渾身の飛び膝をこめかみに受けたのだった。こめかみのはずなのに、全身をくまなく蹴られたように痛いのは神経伝達速度を褒めてあげるべきか。僕の痛覚神経よ、余計なネットワークに接続するな。ダメージは蓄積計算されているらしく、玄関の一撃とは比較にならない鈍痛が体内で乱反射している。きらきら星が見える。
「なんでそこでいちゃいちゃ?」
は……、なんでそこでいちゃいちゃだと思う? 顔が怖くなってますよ? この子、また僕が歓喜に震えていると思ってる。戯れで命を落として堪るか。蛇のじゃれつきは蛙の死亡遊戯だ。不意に朱鷺先輩がベッドから僕の隣へと移るといちゃいちゃと跳び蹴りをカマしたので僕はとても嬉しかった、な物語だそうです。ハワイへの日帰り旅行は一日一回でも多いと思う。
朱鷺先輩に好意的になるあまり、テーブルを挟んだだけの1mもない距離で目撃したことを誤認する。朱鷺先輩に好意を抱いているだけでなく、僕に悪意を抱いているのではないかとすら思えてくる。僕は僕にしか同情してもらえない。かわいそう。
ノりツッコみはやめよう。最初の『面白いおはなし』も結局ノってばかりでツッコめなかったし。正直に精確に、僕は暴力を受けたのだと申告しよう。
「お、お腹が痛い……」
「だいじょうぶ? 笑いすぎだよ」背中をさする先輩。違う。そうではない。全身が痛むためにお腹を抱え込んでいたのでつい、お腹が痛いと言ってしまった。「ズルいぞ」耳元で囁かれる。真実を伝える機会を失った。全身の痛みは笑いすぎが原因になった。ちょっとばかり耳元と背中に幸せを味わえたからまあいいか。よくないが。
「部内の人間だ」
先輩の態度と「スペルマ」だけで事件をそこまで把握してしまうか。
「常に複数の人間が道場で部活をしていましたから、部外者が入ろうとすれば目立ちます。そんな人間はいませんでした。もし我が部の部員に限るのならば、帰り支度の着替えのついでに犯行に及んだのでしょう」
事件における僕の役割がいきなりワトスン君へとランクダウンしたような気がするが、事件を解き明かすことにはやぶさかでない。暴力的ではあっても推理力のある朱鷺先輩のことだ。早期解決に向けてワトスンは協力を惜しまない。
朱鷺先輩は「もし〜ならば」が気に入らないようだ。そこに加えて、部活中に気がそぞらだったことを伝えて不用意に一機減らすことはない。おそらく、残機はあとひとつだ。次に殴られたとき、僕は空に輝くお星様になる。
「秋戸保呂。上加杜智。更屋敷獏徒。田畑帝都。永谷馳。半村富士海。巻鶴椎五。いったい誰から帰った?」
はっきりと読みの甘さを認識した。推理で犯人を見つけるのではなく、裁判で罪人を決めようとしている。裁判長を務めるは蛇の目。
今年になって入部した一年生の名前までチェックしているとはさすが如才ない。僕の名前も、なんの迷いもなく並んでいる。
こんなにも早く、意識を失っていたことを白状しなくてはいけないか。あと一回殴られるか蹴られるかしたら死ぬというのに。どことは言わないが、ここでだけは許してほしい。先輩の部屋を殺人現場にしたくはない。
「永谷くんはサボりで、田畑くんは……」「残り六人」
楽天家というよりは能天気な先輩によって難を逃れた。朱鷺先輩の前ではいつものエアリードのスキルが一割も発揮されていない。口を挟まれて、ようやくわかってきたらしく口を噤んだ。消去法で残ったものが消去されるのだ。朱鷺先輩によって。
「帝都がどうした」
「田畑帝都は先月頭に退部届を受理されています」と、僕。
「残り五人。弁解を考えておけ」睥睨される。
あくまで僕は最重要容疑者として残しておいてもらえるようだ。好物は最後までとっておく主義だけど、朱鷺先輩もそうだとはまるで思わなかった。好物にされているし、タイプも同じだし、意外に朱鷺先輩と僕はぴったりかもしれない。おぞましいことに。
「ねえ、もうやめようよ。わたしは気にしてないし、きみが洗ってくれたからもうなんともないよ。やめようよ、こんなの。好きじゃないよ。しょうがないじゃん。だれかを責めたってどうにもならないよ。終わったことだよ。だからもう、やめようよ」
「巻鶴先輩は顔だけ出して帰ってしまいましたね。部室には入らずに」
憶えている限りの記憶を手繰って、自分の容疑を濃くしてみた。信じられないものを見た顔をする先輩と、それに引き摺られるように僕を見る朱鷺先輩。
「残りは四人。確証ある弁解は用意できたか」
「まったく全然。
僕以外三人の男子部員はどうしていましたっけ、ねえ先輩?」
付き合いきれない、と言うように先輩は首を振って顔を背ける。裁判ごっこは飽きてしまったらしい。
「ねえ」「なあ」不協和音のハーモニ。
僕と朱鷺先輩の重唱は、どちらも先輩の性質を発露させるための呼びかけだった。狡猾な朱鷺先輩が先輩の性質を、もちろん気が付いていないはずがないのだ。先輩と朱鷺先輩の距離は、僕とのそれとはまるで違う。先輩は朱鷺先輩がコントロールしていてしかるべきだ。僕がすべきではなかった。朱鷺先輩の目が驚きに見開いて、これ以上ないほどに灼熱を帯びて攻撃性を示している。
「三人とも先に帰ったよ。誰が誰より先かなんて憶えてない。わたしたちが最後に帰った」
蛇の目が睨む。「僕の記憶も右に同じ」
「一緒に帰ったとしても、着替えは別々。早撃ちすりゃ気付かれない」当てにならない、とでも言いたげだ。
とはいえ、僕だって自分が犯人最有力候補であることは必然の結果だと思っている。発見直前、犯行現場にひとりきりでいたのはほかならぬ僕だ。真っ黒なアリバイをもっている。反証となりそうなことといえば……早漏でないことを今ここで証明しようか。
本気で言ったのではない嫌疑を捨て置いて、朱鷺先輩は裁判を続行する。捨て置いた嫌疑は捨石だった。捨石が水を向け、呼び水になる。
「同じことを繰り返すトレーニングなどしなかったか。そいつがどこかに行っても気付かない時間帯があっただろ」
容疑者が僕ひとりに絞られている。いつの間に三人は容疑を晴らしたのだろう。でも、そのほうが都合がいい。朱鷺先輩の考えていることがよくわかる。あとは、僕がどれだけシナリオ通りに犯人然としていられるかだが。
「走り込みはしたよ。でも、組み手もいっしょにしたし部活が終わるときまでいっしょだった」苛むように搾り出す声。
「走り込みの間はなんでもできたわけだ」先輩が慎重に築いた言葉をあえなく裏返す。
人格を無視した視線をよく『冷たい視線』と言うけれど、朱鷺先輩が僕に送る視線は根本が先輩を思いやってのものだから冷たくはない。人格を灰にする焼け付く熱線。
「せっかくだから自己弁護ぐらいしていけよ」
おまけのような言い草だ。事実、自己弁護など朱鷺先輩にしてみれば飾りでしかないのだろう。逆ギれする、黙りこくる、同情を募る、自暴自棄になる、泣き出す、さてどんな犯人像をお望みかしら。
「グラウンドの走り込みは部活の開始、着替えの直後に行われます。その間はひっきりなしに部室の出入りがあるので、ことに及ぶには無理がありますよね」
「ことに及ぶ」の慣用句に耳を押さえる先輩。「早撃ち」は知らなくても、「ことを及ぶ」には反応してしまうか。これ以上に素っ気ない言葉で表現するなんてできないぞ。僕まで通俗な言い回しをしないといけないのか。
「そうだ。札をかけておくというのはどうです? 女子部員はたった三人。三人がすでに着替えを済まして走り込みをしているのだと知っていれば『女子着替え中。男子なれど入りしとき地獄を見ることにならむ』の札をかけておけば誰も入れません」
「部室の前で待たれたら出られないだろ。時間をかけている間にグラウンドから女子三人が帰ってきたら、誰が入っているのかと訝しまれる。そもそも戸に札をかけられるのか」
自ら立場を危うくすると、自ずと朱鷺先輩が僕を擁護することになるのは滑稽だ。
僕が自分で言ったように、その時間の部室の出入りは激しい。男子が札をいじっているのを見たら記憶に残る。ただの札でも、年頃の男の子にとっては不可侵の聖文である。
「だったら、こんなのはどうです? 部室でヌくことは男子の間では大っぴらになっていることで、最中に見つかろうがまったく不都合にならない、とか」
先輩の顔が赤い。「ヌく」は知ってるのか。聞くに堪えないと耳を塞いでいるのではなく、恥ずかしがっているだけだ。「ことを及ぶ」より「ヌく」のほうが性的表現として生々しいはずだが、どうして反応があべこべなのだろう。違いは自分に向かう悪意の有無か。となれば、先輩の中で男性の性的行為がそのまま嫌悪感に直結しているのではない。先輩の憂慮は精液をかけられたことではないのだ。精液をかけるという行為に内在する、悪意に怯えている。
茶番もたいがいにしろ、と視線が飛ぶ。
「そんな事実はありません。朱鷺先輩が引退して部の空気が弛んでいるのは事実ですが、そこまでソドムにはなりませんよ」
「さっきから聞いていれば、自己弁護になっていない。自供にしても穴のある話ばかり。なにがしたい?」
イラついていらっしゃる。態度が軽佻浮薄に過ぎたかな。最近のトレンドなんですが。
「消去法を用いるのなら、まず最初に可能性を最大限まで広げておく必要があります。例えば複数犯とか、考えてます? 事件の性格柄、単独犯だと思い込んでるみたいですが。考えた結果は無意味でしたけどね。ひとりが自慰行為をしている間、ひとりが戸を押さえておくとか。せいぜいがそのぐらいで、役割分担するほどのことがないから共犯を作る意味はない。ふたりだろうと、ひとりとひとりに数えられる。でも、思索の結果が無意味でも考えることは無意味ではありません」
「結果に表れないなら同じことだ」
素っ気ないな。先輩の一割でいいからリアクションを見習ってほしい。
その先輩は話に付いてこれず、うんうん唸っている。意見を言語化するのを苦手にしているのと同様に、言葉を再構成することも苦手なのだ。無駄話をふんだんに盛り込んだならともかく、実用に即した最小限の言葉による伝達方法ではなかなか先輩に届かない。
「では、結果に表れることをおひとつ。朱鷺先輩は『部内の人間だ』と言いましたね。しかし名前を挙げたのは七名のみ。フルネームにまでして容疑者に印象付けようとしたのは男子部員のみ、ということです。退部した田畑君を除いて、部員は九人。そこから先輩を除くとしても、常冬姉妹まで除いたのは解せません。
わかりますよ。朱鷺先輩がなぜ女子部員を除いて考えさせようとしたかは。でも、不自然でした。寒椿さんはもともと彼氏もちでしたし、冬菊先輩もこの春めでたく彼氏ゲットしたんです。なにも男子部員が部室でヌかなくとも、コンドームに溜めた精液を持ち込めばことは足ります。それは犯行時間短縮でもある。Whoではどうやってもひとりに絞り込むことはできません」
先輩はまだよくわかっていない様子で顔を上げ、朱鷺先輩は痛むのか眉間を揉んでいる。その予想は当たっています、朱鷺先輩。そろそろ立ち位置をそっくり入れ替わりましょうか。
「朱鷺先輩に促されて考慮から外されていた可能性を挙げてみましたが、それは数ある内のひとつです。まだいくらかありますよ。もし我が部の部員に限らないのならば──限る必要がありませんよね。先輩のバッグは窓の真下にありましたから、窓から精液を垂らしてやれば、それだけで状況はハイできあがり。バッグが真下にあるとは限りませんが、それなら窓から侵入すればよいだけのことです」
「されど。武道場の周りはサクラに囲まれているから姿を眩ませることができるとしても、部外者なら校門から武道場へ辿り着くまでにどうしても目に付く。大学とは違うんだ、開放されているとはいえ易々とは侵入はできない」
「可能性を広げるとはいえ、学校外まで含めてしまうほど広範囲にはしませんよ。今はまだ、全校生徒と全教師と全用務員を容疑者に仕立て上げただけです」
僕はいま朱鷺先輩とガチンコ勝負をしているのですから、きょろきょろと可愛く顔を覗き込むのはやめてください。完全に理解を放棄してますね。
「ところで、先ほど気になった点があります。先輩にブレザーを渡したとき、『ブレザーが汚れた。こいつはシャワーを浴びていない。脱いでいる間に汚されたのだ』とご明察を披露していただきました。でも、腑に落ちないんです。『ブレザーを着ているときにブレザーだけが汚れた』となぜ考えないんですか。それに、『シャワーを浴びる時間がない』と判断したのはなぜですか?
前者の疑問にはこう答えることができます。僕が先輩を個人的に手助けできたのは、それ以後に汚れたブレザーを着用する義務のない放課後のできごとだから。でもすると、おや様子がおかしいようです。朱鷺先輩は部活中のできごとだと推察している。ブレザーを着なくてすむ放課後を起点にするのとブレザーを着ていない部活中を起点にするのとでは意味が違います。やった、疑問がギモキングへと深化してしまいました。
後者の疑問へは、現時点の判断材料では答える方法が見つかりません。まったくまるっきり全然皆目さっぱりさらさらありません。どう判断すればそんな風に言うことができるのでしょうね。
実は気になる点はもうひとつあります。こちらは腑に落ちないというほどのことではありません。先輩のことです」
「え、わたし?」話を振られて、きょとんとした顔をする。
「先輩は始め、僕がここに来た理由を察することができなかった。気が動転していることはわかります。たぶん、『慰めに来てくれた』と思ったのでしょう。その通り。しかし、もっと現実的な視点に立って見るなら『ブレザーを返しにきた』が正解です。ブレザーがなければ僕は明日、登校することができない。それは先輩も同じはずなのに、失念してしまっていたのでしょうか。違います。同じではなかった。今日、ブレザーを返してもらわなくても困らなかったのです。なぜなら、朱鷺先輩が女生徒用のブレザーを着て家に来ているから。それを借りればいい。あっと、なぜいま朱鷺先輩が着替えているのかは問わないでおきますよ」
僕を出迎えたのは朱鷺先輩だった。装飾といえばネックレスだけのそんな軽装なら着衣にも手間取ることはない。着替えではなく、服を着るだけだから時間はかからない。
「なぜOBの朱鷺先輩がブレザーを着るのか。ここから疑問点を遡ってゆきます。『ブレザーが汚れたのは部活中だ』と言い、また『シャワーを浴びる時間がない』と言ったのは、部活と帰宅の両方の時間に朱鷺先輩が先輩を見ていたからです。帰宅時間のほうは、先輩宅に着く前から朱鷺先輩が居座っていたとか、僕と先輩を尾けていたとか、はたまた偶然だったとか理由はいくらでも考えられるので考慮しません。問題は部活時間です。学校敷地外からでは、ちょっとした林になっている木立に囲まれた武道場の中にいる先輩を見ることはできません。なので、学校に入ったのでしょうね。目立たないようにして、ブレザーを着て。そう考えれば、すぐにブレザー返却を必要としなかった先輩と犯行が部活中だと断言した朱鷺先輩に感じた疑問を無理なく同時に解消します。
ではもう一段、遡りましょうか。朱鷺先輩は『部内の人間だ』と言いつつ、男子部員に限ったのはなぜでしょうか。ここまで来たらもう自明です。それは、部外者であり女である朱鷺先輩が犯人だからです」
先輩は朱鷺先輩を見つめている。朱鷺先輩は俯いたまま動かない。
「そういえば、あのとき先輩『とき、とき』とうわ言のように呟いていました。支えがほしくて朱鷺先輩の名前を呼んでいるかと思いましたが、誰がやったのか感付いていたのかもしれませんね」
ダメ押しの一言は、しかし聞いているのかいないのか。最後まで語りきるまでもなく、状況はもうひっくり返すことのできないところまで振りきったようだ。先輩は、部活中に朱鷺先輩と会っているときのことを思い出しているのだろう。僕が現実世界から旅立っている間に、逢引している。なんのことはない、その時間に武道場には誰もいなかったから僕が疑われたのだ。
「覚悟は、できているんだろうな」俯いたまま訊ねられた。
「はい」一年以上前から。
氷が溶け出してもお茶の濃さが変わっていなかった。この氷は水を凝固させたものではない。お茶を凝固して作った氷を同じお茶の中に入れているから、氷が融解しても薄まらないのだ。氷付きのお茶が湯飲みに淹れてあるのも、見た目よりも実利をとったためだろう。僕がそういう人間だと知っているから。ただの天然だからではない。この湯飲みは陶器で、大きさのわりに重さを感じない。材質そのものの熱伝導率は陶磁器も硝子も変わらないが、焼き方や形によっては異なってくる。冷めにくい湯飲みは当然、温まりにくい湯飲みともいえる。
その場を繕うように適当な注文をした僕に、先輩は要求に合う見繕った適当なお茶を淹れてくれた。いつもそうだ。心尽くしの振舞い。
朱鷺先輩の視線が先輩に向けられる。先輩は今にも泣き出しそうな顔だ。
「なんでっ……そんなっ……っく……うぅ。わっ、わたしは……わたしは朱鷺を──った。──ったのに。好きだったのに。イヤだ、嘘」
「俺がやった。理由はない。気持ち悪いと気付いたからだ」
朱鷺先輩はドアを開けて、
「二度と来ない」
部屋を出て行った。
呆気なく素っ気なく先輩は拒絶された。全幅の信頼を寄せていた朱鷺先輩に拒絶された。
唇に留まらず、肩が──全身が震えている。全身で、挫折と蹉跌と撤退と失態と後悔と自戒と痛恨と悔恨と不調と自嘲と破鏡を感じている。無理からぬことだ。なにより拒絶されることに恐れる先輩が誰より拒絶されたくない相手に拒絶されたのだから。
「先輩?」肩に手をかける。
「触らないでっ」振り払われる。
「先輩……」もう、一度でも触ったら壊れそうで、触れられなかった。
「ごめん。ひとりにして。お願いだから、ひとりにしてください」
居たたまれなくなって部屋を出た。玄関扉を見たとき嫌な予感がして逡巡したものの、朱鷺先輩が待ち構えているということはなかった。通りを見渡しても、すでに朱鷺先輩の姿はない。安堵すべきか、しかし物悲しい。これで正解だったのかわからない。気に入らないから作り直そうとして、結局は破壊しかしてこなかった虚脱感が身体に残留している。
角を曲がったところに、いた。戦闘体勢ではなく、身体を二つに折って上半身を丸めて大真賀朱鷺がいた。
「朱鷺先輩?」肩に手をかける。
デジャヴを感じたが、ついさっき先輩にしたことそのままだった。
「あの、申し訳ないとは思ってますよ。でも──」
「っ……くくく、くっくっく。くははっ! なーにが『申し訳ない』だ。死者に鞭打つダメ押しまで念入りに入念にやっておきながら」
怒っている? いや、笑っている。『面白いおはなし』の悶絶とは逆パターン。なんと、鉄面皮の朱鷺先輩が今は全力で笑っている。
「まさか俺が、カウンタ喰らってその上、マウントまでとられるとは。まさに一本取られた、だ。くっく。
お前、出てくるの早すぎるぞ。俺が気を利かせて出て行ったんだ。キスの一発や二発は、もちろんブちカマしてきたんだろうな」
僕が朱鷺先輩に追いつくまでに、人物の入れ替わりトリックが使われていませんか。なんか、途方もなく怖いです。朱鷺先輩のキャラクタに、『先輩風吹かしたい』が混じってる。今日は、新しい朱鷺先輩発見デーか。
「どうした。やってないのか。まーだまだまだあいつのことがわかってないな。ははん。
若人よ、あいつのどこに惚れたんだ?」
今まで感じてきたのとは別の意味で逃げ出したい。でも、これは通過儀礼というものだろう。先輩の引継ぎ、といったら怒られてしまうか。
「人の心を見通せるのに、それに苦しんでばかりで利用することなんかこれっぽっちも考えていないところ。他人の悩みに人一倍悩んでいながら、明るく振舞ってしまう。僕はそんな先輩を支えてゆきたい」
まじまじと目を見つめられる。蛇の目はどこかに消えていた。
「薄幸美人か。くく。全っ然、ダメだな。なにもわかっちゃない。『人の心を見通せる』だ? なにに期待してるんだ? そんなことは誰だってやっている。そんなこといちいち気にしてたら不利益こうむるから無視しているだけだ。あいつを理解したいのなら、肌に触れた人間、話をした人間、目に見えた人間、すべての人間の心に意識的に注意を向けることだな。決して逸らさずに。くはは。できるか、お前に。あいつに『氷』と評されたお前に」
僕は氷。それは喫茶店で告白したときの比喩話だ。先輩から聞いたのか。それとも、日頃から先輩をストーキングしているのか。違う。あの日の待ち合わせ、僕は「まだかまだか」と入り口に注視していた。先輩がテーブルに着いてからも、状況に即応できるよう周囲への観察は怠らなかった。あのとき、喫茶店に朱鷺先輩はいない。店外に声が漏れることもない。
「お前は俺とあいつの関係を見誤っている。あいつはいつでも居場所がわかるように発信機を身に付けている。あの日は集音機も付けていたっけな。なにを話しているかよく聞こえた。『乞食がそこにいた』だっけか。乞食くん、俺からあいつを奪ってどうするつもりかね」
首を屈めてネックレスを外す。見ると、飾りのように見えたのは小さな鍵だった。ネックレスに鍵が通っている。
「『でも』、なんて続けようとした? 『申し訳ないとは思ってますよ。でも』の続きだ。『朱鷺先輩ならすぐにまた信頼を勝ち取れますよ』とか、か。無理だな。あいつはなかなか捨てないが、一度捨てたら二度と拾わない。そういう性格だ。一度、自分自身を捨てている。拾わせるのに難儀したものだ。運よく拾わせることができたものの、もう二度とできる気がしない。
お前が氷なら、あいつは硝子といったところか。喩えがステレオタイプなのは勘弁しろ。氷だって、笑ってしまうほど古典的だ。硝子は割れやすく壊れやすく砕けやすく脆い。もし、お前があいつをダメにしてくれたらブち殺すから、な」一足飛びで間合いに踏み込まれ、正拳突きを叩き込まれる。
それ、先輩を壊そうとする前に僕が壊れますから。人生のゲームオーバ。バッドエンドのデッドエンド。生けるものよ、さようなら。死せるものたち、初めまして。これからお世話になります。仲良くしてください。
──あれ、痛くない。神経がついにイカれてしまった。狂ったか。むしろ、幸せになってしまっている。
「エンドルフィンって知ってるか?」
「イルカ?」
「くははははっ。いいぞ、あいつと同じ聞き間違いすんな。鎮痛作用と多幸感をもたらす脳内麻薬だ。神経科学には詳しくないから質問は受け付けんぞ。理論がわからずとも、俺はそれを扱える。部活で試していたらできるようになった儲けものだ。同じ相手に二度も殴ればコツを掴めるさ。祝儀だと思って、その快楽を受け取っておけ。氷と硝子の似たもの同士諸君。
関係をブち壊してくれたとはいえ、感謝しているんだ。これであいつは心の平静が保てる。壊れずにすんだ。直したものがまた壊れるのは見たくないからな。しかしこれで、ようやくあいつの管理から離れられるというわけだ。任せたぞ」
表彰台に上がったメダリストのごとく、ネックレスを賜う。
「なんの鍵だか、わからないか。お前ならすぐにわかるだろうが、ヒントをやろう。あいつは告白を受けた喫茶店でなにも頼まなかったし、今日も三人分のお茶を用意しておきながら自分だけ手を付けなかった。学校生活でも最低限の飲食しかしていないはずだ。なぜだろうな」
わかるか。お口に鍵付きチャックでもしているのだろう。
「くっはっ。どちらにせよ、なんにせよ、早く寄り添ってやれ。あいつはお前を必要としている」
朱鷺先輩の目には笑いすぎて涙が浮かんでいる。それは一〇割、愉悦によるものだ。絶対に。“忍び寄る夜に因る反魂香” closed.
-
2008/09/12(Fri)03:44:55 公開 / 模造の冠を被ったお犬さま
http://clown-crown.seesaa.net/
■この作品の著作権は模造の冠を被ったお犬さまさんにあります。無断転載は禁止です。 -
■作者からのメッセージ
【すべてがIFになる】を思い出します。私の登竜門デビュ作です。森博嗣を知っている方がどれほどいるかわかりませんが、彼のメフィスト賞受賞作そしてミステリデビュ作となったのが【すべてがFになる】です。タイトルが似ているのはもちろん、私が【F】のタイトルをもじったから。内容は、というと。【F】は本格ミステリ(あるいは新本格ミステリ)と呼ばれる伝統的な推理小説だったのに対し、【IF】は奇妙な持ち味があるものの恋愛模様を綴った変哲のない書き物でした。ただ、ほかの書き物と違うのは登竜門の投稿システムに着目してそこに叙述トリックめいた引っ掛けを施していたことです。今作は、図らずも【IF】のときと同じような効果を生み出しました。私も驚いているのです。ふふふ、誰も仕掛けていないトリックに騙されるとは幸せな人たちです。前回更新分は前座で、今回更新分こそ真打です。楽しんでいただけたことを願い、読んでくださったことに感謝します。
あ、感想欄でのネタバレはご遠慮ください。
作品の感想については、登竜門:通常版(横書き)をご利用ください。